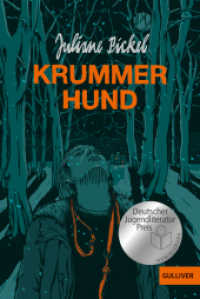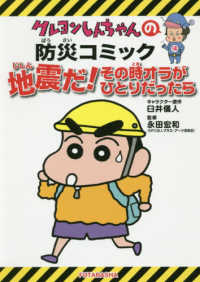出版社内容情報
イギリスの文芸復興期にあって,フランシス・ベーコンは人類への奉仕という強い使命感とその恵まれた才能によって,学問の革新という一大事業にたちむかった.本書でのベーコンはその思想と方法に従って,すべての学問領域にわたって過去を点検し,全体を展望しながら,未来への方向を示している.ベーコンの中心的著作のひとつ.
内容説明
人類への奉仕の手段として真理の探究の道を選び、学問のあるべき姿を構想した「近代学問の父」ベーコンの主要著作。英語で書かれた最初の哲学書と言われる。「知識の世界の地球儀」をつくって学問の過去と未来を照射する試みの一環として、まず学問の尊厳と価値を説き、続いてその進歩のために何が必要なのかを明らかにする。
目次
第1巻 学問と知識とのすばらしさについて(学問のこうむった不信と汚名;学問のとうとさ)
第2巻 人間と神とに関する学問の進歩のために、何がなされたか、また何が欠けているか(人間(の知力)による学問の区分
神(の啓示)による学問の区分)
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
13
学問の人による区分と神の啓示による区分という考え方が面白かったです。歴史、詩、哲学という実学でない部分を深めていきたいと感じました。2021/09/11
kaya
10
ベーコンの言及は知識や神学だけでなく、医学や善についてなど非常に広範囲に渡っています。安楽死や患者の負担を極力減らすことなどを医術に携わる者に求めていて、彼の鋭さを感じました。しかしとても気になったのが教育に関する記述が少なかったこと。当時の教育は国指針ではなく、一定のカリキュラムの設定がなかったから?学問と教育とは別ものなんだということをひしひしと感じた一冊でした。それにしてもジェームズ1世に媚びまくってる文章が何とも言えず… 当時はこんな文章じゃなきゃ読んでもらえなかったのかな。2014/05/07
Fumoh
4
ベーコンは若い頃から『大革新』という著作を志していた。それはアリストテレスから流れをくんだスコラ学派の権威を打破するためであった。ベーコンはこう考えたとされる。当時はコンパスの発見、印刷術、また新大陸・新航路の発見と次々に科学の進歩がもたらされていた。しかしそれらの発見全ては、スコラ哲学とは何の関係もないところで見出された。哲学の分野は伝統の権威にすがっていて進歩が全くない。それでいいのか……と。ベーコンは学問の改革をする意欲を見せ、またそれに見合った才能があるという自負があった。家系の伝統から、2025/01/03
Saiid al-Halawi
4
「まず第一にヨーロッパにはずいぶん多くのりっぱな学院が設けられているのに、それらはすべて専門科目[神学、法学、医学]に専念して、教養科目[哲学と一般原理の研究]をやる余裕のあるものが一つもないことを、わたくしは不思議に思う」p.1172015/10/27
BATTARIA
3
書かれた時代が時代だし、活字が小さいこともあって、最後まで読み切るのが、本当に大変だった。 示唆に富む箇所はいっぱいあり、本当はメモしながら読みたいところだけど、通勤電車じゃムリだしなぁ。 それにしても、こうしたトータルで学問を論じ、学ぶこと自体を学ぶ。 いまの世の中、この人のような存在が、あまりにも少な過ぎる。2016/02/29