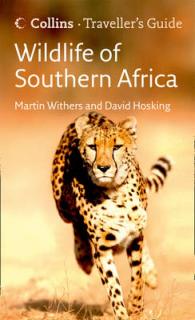出版社内容情報
宗教改革前夜のヨーロッパの戦火の中からあげられた良心の叫びであり,平和維持の具体策を提唱した近代最初の平和論の古典.エラスムスは,人間から見棄てられた平和の神の口をかりて,戦争の原因となった為政者・権力階級の無責任と欺瞞を鋭く告発し,愛と平和を望む民衆の自覚と協力を呼びかける. (注・解説 二宮 敬)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
15
ルネサンス期は異教徒との戦争が他国との戦争な変わる時期でもある。カトリック教徒の著者は、ルターの提起した『95ヶ条の論題』(1517)の聖書中心主義を擁護しつつも教会の分断を促さぬようルターに提言する。同年、神の教えを人間を主体として理解し、争いを起こさないという聖書の教えを守る態度を表明した本書は、言語や国家に囚われない同じ人間という理念を提起して民衆側からの非戦を訴えた。その後カトリックとの闘争を続けるルターとの論争やカトリック側の禁書扱い等で孤立する著者だが、本書の人文主義的理念は後世に継承される。2022/05/11
twinsun
14
戦争も土地の配分も婚姻も人間が決めたことで神には責任はない。人間が始めたことは人間に責任があり神の名のもとに正当化すべきでないし争うべきではないだろう。国家や権力の現実に縛られず、それぞれの言語や民族の視線で平和を求め違いを超えて愛し合うことを基礎に現実に対処するべきであるが、そのような態度は自己解釈の神を利用するものと敵対せざるを得ない。神が全きもので存あるならば人間の願いを聞くのではなく良き自分の教えを聞くことを望むであろう。そこに流血や略奪は含まれないはずだ。2022/04/25
S.Mori
14
素晴らしい本でした。平和の神が戦争をしないことの大切さを、ユーモアたっぷりの口調で訴えます。16世紀に書かれた本ですが、現代でも十分通用する普遍性を持っています。エラスムスはいろいろな人たちを槍玉にあげているのですが、一番批判されているのはキリスト教関係者です。平和を最も重視しなければならない人たちが、戦争の原因になっていると厳しく批判しています。これは現在でも当てはまることででしょう。宗教が原因の一つになっているテロや紛争が続いています。それを考えると悲しい気持ちになるのは避けられません。2019/09/11
RED FOX
13
「キリストの何よりも忌み嫌われた戦争が他ならないキリスト教徒の間でとびきり華々しく繰り拡げられているのを目撃している限り彼らトルコ人が」中世欧州の戦争の多さに驚く。著者の舌鋒の鋭さに感動する。2025/06/16
泉を乱す
13
マキャベリ「君主論」読んでドーパミンが出たんだけど、こちらを読んでセロトニンが出た2023/01/07
-

- DVD
- かんなぎ 6(通常版)