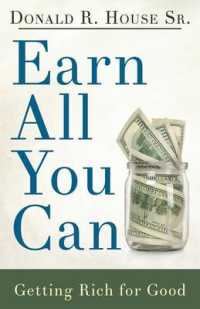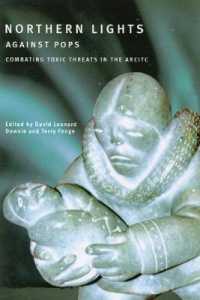出版社内容情報
司馬江漢に先立つ日本初の本格的な洋風画である秋田蘭画を初めて評価した日本画家・百穂による貴重な文献。平賀源内に手ほどきを受けた秋田藩士・小田野直武や藩主・佐竹曙山らの試みはわずかの期間で終わるが、その輝きは近代を告げる閃光だった。元本は一九三〇年に小社より三〇〇部刊行。カラー図版多数。(解説=本橋理子)
内容説明
司馬江漢に先立つ日本初の本格的な洋画風である秋田蘭画を初めて評価した、日本画家・百穂による貴重な文献。元本は1930年に美術書として300部刊行された。平賀源内に手ほどきを受けた秋田藩士・小田野直武や藩主・佐竹曙山らの試みはわずかの期間で終わるが、その輝きは近代を告げる閃光だった。
目次
1 佐竹曙山と平賀源内
2 平賀源内と小田野直武
3 曙山・直武小伝
4 解体新書図巻
5 画法綱領と画図理解
6 曙山の洋画論
7 洋画の技法
8 虫類、植物及び鳥類の三写生帖と和蘭軍人図譜
9 曙山、直武の作品
10 曙山、直武系の作家
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
26
2012.03.20(つづき)平福百穂著。 M26、黒田清輝の帰国、一気に新派系洋画が浸透、台頭。M29、校長岡倉天心、黒田清輝を迎え入れ、「日本画科」と「西洋画科」(のち、油画科)に分かれた。文展開設以前。日本美術学院系の画家。岡倉天心。対して、「自然主義」の傾向、とくに日本画を目指す、志す若手画家たちの小さな研究団体やグループが。そのうち、「天声会」。結城。天声会の理念的立役者、東洋美術史、美術評論家大村西崖(1867-1927)2012/03/20
i-miya
26
2012.03.20(初読、初著者)平福百穂著。 2012.03.18 (カバー) 司馬江漢に先立つ日本初の本格的な洋風画である秋田蘭画を初めて評価。日本画家、平福百穂による貴重な文献。 原本、1930、300部限定刊行、岩波書店から。平賀源内から手ほどきを受けた、秋田藩士小田野直武や藩主佐竹曙山らの試み、わずかの期間で終わるが、その輝きは、近代を告げる曙光だった。2012/03/20
i-miya
25
2012.03.24(つづき)2012.03.23 第一図、西洋婦人像、平賀源内。 鹿田氏。絵の具の十分乾かぬ上を、木筆もしくは金属制のごときもので、ぐいぐい描いてある。宋紫石。司馬江漢、1811、文化8年「春波桜筆記」宋紫石は、長崎に遊んで、沈南びん(しんなんびん)の高足(熊代)熊(ゆう)斐(ひ)に学ぶ。後、宝暦8年、清客、宋紫岩について、南ひん風を江戸に伝えた。司馬は後、長じて、狩野古信に学んだ。和画は俗である、と思ったから宋紫石に学んだ、と云っている。紫石は当時、長崎写生派の名手として重視されてい2012/03/24
i-miya
18
2012.03.29(つづき)平福百穂著。 2012.03.27 小田野直武32歳、の死。平賀源内、発狂して学どうを死に至らしめ、12月に獄に下り、遂に牢死したこと。四.解体新書図巻。 小田野直武の画法が江戸詰めになって著しく上達したことは疑いない。2012/03/29
i-miya
17
2012.03.25(つづき)平福百穂著。 2012.03.23 一.興に乗じて酒を呑むとも、酒に乗じて興を飲呑むこと勿れ。 一.首のあれば、何の憂きことかあらん。 小田野氏の家に、源内のこの著、珍蔵していたが、M33(1900)の大火で焼失した。 佐竹-三味線掘の本宅。 三.曙山・直武小伝。 曙山、38歳の死。 学風は朱子学、藩学=明徳館。 天性、虚弱、多病。 そのためか、体質よりjくる鋭さがあった。 2012/03/25