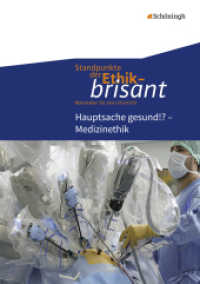出版社内容情報
美術批評の第一線に立ち美術館行政に深く関わった土方定一。本書は西欧の技法摂取を江戸に遡り、日本画と洋画の抗争を戦後へ辿る。日本美術を世界に位置づけた史観と解釈が鮮やかな名著。図版多数。
内容説明
美術批評と美術館行政への功績でしられる土方定一は、みずからの眼で絵画や彫刻を確かめる“経験としての美術”へと読者を誘う。この本は西欧の遠近法や明暗の摂取を江戸期にさぐり、日本画と洋画の抗争や相互影響を戦後までたどる。日本美術を世界美術の中におく史観と人間への洞察ひかる名著。図版多数。
目次
1 伝統美術と近代美術
2 初期洋画のプリミティヴィスム
3 岡倉天心と民族主義的浪漫主義
4 黒田清輝と外光派
5 日本画のなかの近代
6 近代と造形
7 日本画の近代の展開
8 近代日本の彫刻
9 社会思想と造形
10 二十世紀の近代美術
11 戦後
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
28
神奈川近代美術館館長でもあった著者の日本美術とくに江戸時代からの技術を近代美術の中に探っての論考です。岡倉天心や黒田清輝についてはかなりな力の入れようです。私は美術(特に絵画)が非常に好きなので写真でなかに紹介されていますが贅沢をいえば口絵でカラーにしてもらいたい気がしました。2014/11/26
sabosashi
17
岡倉天心あたりから始めて洋画と日本画の摩擦を論じ、ヨーロッパの動向に注意をはらいながら戦後の動向にも眼を走らせるなど実にまんべんなく説明していくのにすっかり感心してしまう。なんという博学か。しかもあちこちに思い入れたっぷり。戦没した少壮の画家への思いは深い。メジャー級以外の日本近代の画家は名のみ存じているという場合が多いが、ここではしっかり歴史的(もちろん美学的も)コンテキストにつなぎ合わせてくれる。さほど期待はしていなかった著書であるが啓蒙的すぎた。2025/11/15
1.3manen
11
岡倉天心は、同時代の民族主義の思想を共有していた。他方、精神と造形の故郷を見、近代化しようとする実践指導者となっていた(56頁)。黒田清輝の「舞妓」はモノクロのため、油絵とは思われるが、なかなか見入った(70頁)。浅井忠の「春畝(しゅんぽ)」は農業、鋤を畑に入れる、牧歌的な農村風景の明治21(1888)年(75頁)。上半分明るい。藁ぶき屋根、梅の花、菜の花畑。下半分は深緑色の麦畑の畝(74頁)。荻原守衛の「文覚」は筋骨隆々の腕組みした男の彫塑(157頁)。津田青楓と河上肇が交友(188頁)。知らなかった。2013/09/14
ラウリスタ~
9
日本の近代美術とは、伝統的な日本画と外来の洋画との対立と吸収そして対立の歴史。西洋の写実的な絵画に衝撃を受けて始まった稚拙ともいえる洋画崇拝と、それの反動としての日本画の見直し、そして戦前戦中の日本画、そして戦争画の席巻。こんな辺境の地においても、明らかにかなうわけもない目標を見据えて闘い続け、日本近代美術の嚆矢となる作品を作り続けた先人達には頭が下がります。過度の日本美術称揚も嘘だし、安易な(低次元での)日本美術否定も論外。果たして、日本が真の文化大国になる日は来るのか。2011/05/13
ぴよぴよーーーーー
4
江戸後期から戦後期まで、常に追求され続けた西欧からの斬新なスタイルに日本古来の独特な様式・画法が抵抗するといった図式で近代美術史は展開されてきた。本書はそういった美術史を作品のスタイルや作家の派閥など、時の流れに伴う変化にも着目して追いかけてゆく。 画家・彫刻家1人1人の代表作が挙げ連ねられているのはいいが、もう少し参考写真を増やしてほしいとは思った。ともあれ、今まで読んだことのないタイプの美術史の書で、なかなか興味深かった。2015/01/11