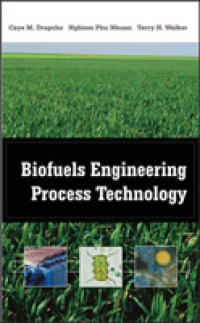内容説明
幕末明治期の天才画家河鍋暁斎。その群を抜いた画力に惹かれた弟子の中には、かの鹿鳴館の設計者コンドルがいた。「暁英」の画号を持つ愛弟子が、親しく接した師の姿と、文明開化の中で廃絶した日本画の技法を克明に記し、暁斎の名を海外にまで広めた貴重な記録。
目次
第1章 暁斎の生涯
第2章 画材について
第3章 画法について
第4章 技法の実例
第5章 署名と印章
第6章 暁斎画コレクション
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
34
NHKの新日曜美術館で政府のお抱え建築士であるジョサイア・コンドル氏から見た師匠、河鍋暁斎の特集をしていた時にこの本が紹介されていたので興味を持ち、読みました。読むと川に流されていた罪人の首を隠して模写していたことや修業時代に帯の模様を描くため、女中を追いかけまわして破門されたとか、写真のように一瞬を頭に記録して描いていたことなど、NHKはこの本を忠実に再現して構成されていったんだなと気づきました。ただ、図は掲載ページがバラバラなので見難いです。2014/04/18
tsubomi
9
2020.01.12-03.30:鹿鳴館などを手掛けた建築家ジョサイア・コンドルの河鍋暁斎論。私の中では建築家というイメージが強く(実際そうなのですが)、日本画を習っていた、それもかの有名な河鍋暁斎に弟子入りして!ということ自体が衝撃的な事実でした。著者が趣味で日本画についてさらっと書いた本かと思いきや、きちんと暁斎に弟子入りして、写生旅行にも同行し、葬儀まで取り仕切っていたとは!師匠の人生、絵の道具、色の使い方、表現方法、表装方法など微に入り細に入り紹介。これほど詳細な日本画の紹介書は今では貴重な宝。2020/03/30
鮭
8
著者は鹿鳴館を設計したことでも有名な建築家ジョサイア・コンドル。日本画家としては「河鍋暁英」の号をもつ。そんな彼が、師であり友でもあった絵師「河鍋暁斎」について、生い立ちから使用した画材・画法、落款に至るまでを解説した書。コンドルが暁斎と交流したのはわずか8年(1881年暁斎に入門、1889年暁斎没)であったことを考えると、どれほど暁斎に心酔していたのか本書から垣間見える。画法については事細かく解説しているので読み物としては味気ない部分もあるけど、暁斎の作品を鑑賞する上で最良の手引書になりそう。2020/10/04
色々甚平
6
河鍋暁斎の弟子が書いた本なので、普段の生活とか人となりの本かと思ったら、技法についての話などが半分あったため、日本画や絵を学んでいる人には何かヒントがあるかもしれない。好きな絵のポイントにも触れられていたのは描いている姿を思い起こせるようで良かった。狩野派のあたりの流れは思っていたとおりの姿で嬉しい。外国人が日本人の日本画に弟子入りし、その弟子を大切にしていた話も少し入っているのも見どころ。2018/04/15
1.3manen
5
新奇異様な筆致(21頁)。1831年生れ(29、275頁)。狩野派の低落した実力を密かに軽蔑(41頁)。墨絵の独特な描写。濃淡を白と黒の微妙な濃度の違いで使い分ける。鯉の絵は「鯉魚遊泳図」(105頁~)など。鱗の描法は細密かつ科学的(106頁)との評。128-31頁の鳥や竹の墨絵もまた、雰囲気がいい感じである。真の画家はある部分をわざと表現せずに残して悦に入る(157頁)。想像させる余白なのだ。これも創造の楽しみなのだ。後半の第6章は美術館さながらの作品展覧頁。本書を読むと、床の間に掛け軸の一つもと思う。2013/04/02