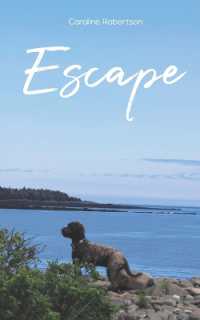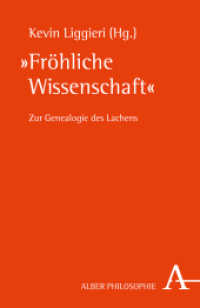出版社内容情報
都会の経済活動について筆を進め,商品の労働価値説を展開し,物価の体系性をも指摘する第5章.次いで第6章では,学問と教育の問題を俎上に.学問の前提となる思考力から説き起こし,当時の学問状況を概観してゆく.(全4冊)
内容説明
著者は、人間の生産活動における労働の役割を重視した。本巻収録の第五章では商品の労働価値説を展開し、物価の体系性をも指摘する。次いで第六章では、「文明学」の観点から既存の学問を論じ、都市における技術の多様性と剰余労働が学問の発達を促すことを示す。
目次
第5章 生計とその手段としての所得や技術およびこれらに伴うあらゆる事項、その内部に横たわる諸問題について(糧(としての賃金)および所得の真意と説明 所得は人間の労働力が生み出した価値である
生計を営むための手段とそのさまざまな方法について
奉公は生計として自然な方法ではない
埋蔵物や(いわゆる)宝物を掘りあてて財産を得ようとするのは、生計を営む自然な方法ではない
権威は財産を得るのに役立つ ほか)
第6章 学問の種類、教育の方法、それらに関連するあらゆる事項、ならびに序言と附言(人間の思考力;行為から生じる世界は、思考を通じて実体化される;経験知、それはいかにして形成されるか;人間の認識と天使の認識;預言者の認識 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koning
25
商売の話と学問の話ってことになるんだろうけど、うん、中世だよ(笑)。そして、やはりどうにもある種愚か者を見下す感がたまりません(え。2葉原書からの図表類の画像が見開きで付いてくるのがこの巻なんだけど、文庫だと細かいところがつぶれちゃってて見えねぇ!のがとても残念でございます。2015/11/15
有沢翔治@文芸同人誌配布中
7
学問と技術について。「ある技術では、労働力以外のものを伴う。たとえば木工には木材が、機織には紡糸が要る。しかし、いずれの技術においても、労働力がより重要であり、その価値ももっとも大きい。たとえ技術以外のものによって儲けや利得を得たとしても、労働なしにはその利得を得ることはできないのであるから、それに要した労働の価値をこれらの利得の中に含ませねばならない」労働価値説につながってくる。http://blog.livedoor.jp/shoji_arisawa/archives/51509884.html2020/01/02
AR読書記録
5
ます面白かったのが、“ゲルマン人(あるいは古代エジプト人やローマ人など)の隠された財宝”を求めるトレジャーハンターがけっこういたらしいのがわかること。著者は単に詐欺的行為だって切って捨ててるだけなんだけど、なんかこうアラビアンナイトなイメージに合って想像すると楽しい。それから医術についての記述で、食べた物が血肉になるまでを解説している部分。違うんだけど、かなりそれらしく、わりと説得されちゃう。そして最後の文字魔術の項。占卜表とそれの使い方の解説まで載っているが...うーん、難しくてわからん。残念><2015/02/04
壱萬参仟縁
5
農業は心の弱い人々や田舎の民のように貧困にあえいでいる人々の生計の道である(43ページ~)。農業こそ貧困を防ぐ手立てでもあるが、現代は豊作貧乏と凶作貧乏で両方とも困窮となってしまう逆説があるのはどうしたらいいかと思う。商人につきものなのはずるさ、口論、機敏、論争、執拗さ(52ページ)。全く経済人そのもので嫌な気分。学問を究めるには、原理や法則を理解し、問題を熟知し、細目を展開できるような習性(そういうことになっているということ)をマスターすること(149ページ)。学者間の暗黙の了解が重視。それでいいのか?2013/01/05
Saiid al-Halawi
2
中世感満載な科学談義。思弁神学!2011/04/14