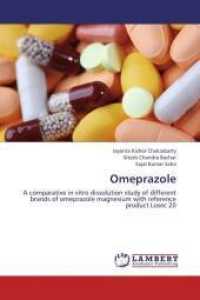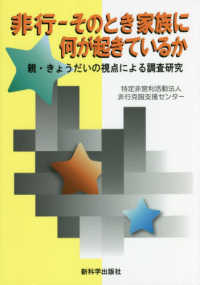出版社内容情報
大民族からの圧迫にさらされながらも固有の文化を維持し続けてきたモンゴルの人々.著者が自ら探索し明るみに出した貴重な古文書を手がかりに,モンゴル人の歴史意識の発展をたどり,広い視野から草原の民の歴史と文化を語る.
内容説明
広大な草原の遊牧生活とチンギス・ハーン―周辺の大民族からの圧迫にさらされながらも固有の文化を育み維持しつづけてきたモンゴルの人々。著者が自ら探究し明るみに出した貴重な古文書を手がかりとして、モンゴル人の歴史意識の発展をたどり、豊かな文学の実りにふれて、草原の民の文化と歴史を広い視野から紹介する。
目次
第1章 EX TARTARO―地獄から来れる者ども
第2章 北京からモスクワまで―北京とモスクワの間
第3章 焼けこげた過去の遺物
第4章 デンマーク人らがモンゴルの歴史文書を発見する
第5章 最後の大ハーンの悲劇
第6章 モンゴル人のニーベルンゲンのうた
第7章 ラマ僧はシャマンを駆逐する
第8章 雑記帳に見る政治
第9章 英雄ら再び馬を馳せる
第10章 天幕の中の劇場
第11章 地の神々それを禁じ給う
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
itokake
11
【読書で世界一周】堅いタイトルからは想像ができないほど面白かった。写本を探す所から歴史は始まる。20世紀前半、写本集めは現地のモンゴル人から買い取るだけでなく、老人が死ぬ前に埋めた本や、ネズミの巣(かじられて巣材にされていた)まで!そういうフィールドワーク的な記載もあれば、物語のように歴史を語る部分もある。モンゴル人にとって中国への関心は略奪品。略奪品で飽満してしまうと、平和で満ち足りた気持ちになった。そこで西方の富裕なイスラム教徒の都市や国々と貿易を望んだ。シンプルだが本質をつく行動原理に納得。2025/04/07
壱萬参仟縁
10
手書き地図(139頁に2枚)。古地図というのは、人間が描いているため、実に手づくり感、人間的な感じがする。正確さというよりも、史料として価値があるのだ。261頁には印刷屋の写真がある。4世紀以来、漢人がしてきたように、一枚一枚の板から刷る(267年)。330ページには日本の軍隊がつくったというポスターがある。中国語とモンゴル語と絵から成っている。相撲ではモンゴル出身の力士が増えている。その日蒙の関係を考えると、似たような顔の人もいるので、起源はここにありそうな気もしてきた。2013/05/02
ドウ
6
邦題に惹かれて読んでみた。が、モンゴルに明るくない人間がモンゴルの歴史と文化を学ぶには、内容が体系的でないし、本書の主題は、むしろ北欧・中欧の学者たちによるモンゴル語写本蒐集史の趣がある。彼らがモンゴルに惹かれる理由も読み取れない。大陸の東西でロシアの圧迫に耐えてきたという同胞意識のようなものだったのではないか。2020/09/25
酔うた
2
ハイシッヒ1964年の作「民族は歴史を探し求める」の1967年日本語訳の2000年リバイバル。モンゴル人の歴史は中国・ロシア・ヨーロッパ、そして日本との関りの中で、躍動し、そして苦しみの中にある。この一冊の中に、なんとその内容の豊富なことか。それは著者の学問的人格が大きい。学問で歩かないかは反証の機会に開かれていること。日本の文系学問の見習いたいところ。2019/08/27
ふら〜
1
再発見された埋もれていた文献を手掛かりに、モンゴルの歴史、文化を見直していこうという本。再発見された本は(保護を名目に。ただ実際戦火や悪い保管条件を逃れた本もたくさんあろうが)モンゴルから返せ、と言われないんだろうかと別のところが気になる。2021/07/25
-

- 和書
- まっすぐに西へ