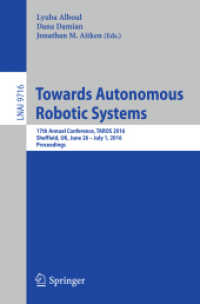出版社内容情報
二世紀後半,ギリシア全土の山間僻地まで精力的に取材して記した詳細な案内記.巧みに設定した順路に沿って名所旧跡を案内し,そこに伝わる行事,宝物,ゆかりの神話を語る.他の文献にはない伝承を数多く伝えており,現代の旅行者にとっても秀抜な旅行案内であると同時に,古代ギリシア研究に不可欠な基本資料である.
内容説明
2世紀後半、ギリシア全土の山間僻地まで精力的に取材して記した詳細な案内記。巧みに設定した順路に沿って名所旧跡を案内し、そこに伝わる行事、宝物、ゆかりの神話を語る。他の文献にはない伝承を数多く伝えており、現代の旅行者にとっても秀抜な旅行案内であると同時に、古代ギリシア研究に不可欠な基本資料である。
目次
第1巻 アッティカ(アッティカ(スニオン;アテネの外港ペイライエウス;ファレロンとその近辺;ファレロン街道からアテネ市内へ ほか)
メガリス(メガラ地方)(メガラ古史;メガラ市内案内―テアゲネスの泉場など;アクロポリスのひとつ「カリア」;メガラ市内北側と近郊 ほか))
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
OZAC
11
人名・地名とその関係性を把握するのが大変で、訳注といったりきたりを繰り返してようやく読了。古代ギリシアの地誌というとストラボンの『ギリシア・ローマ地誌』が真っ先に思い浮かぶが、こちらはパウサニアスによって書かれた観光案内書である。が、観光案内書というものの中身はがっつりギリシアの神話や歴史が盛り込まれていて読み応えは十分ある。一番読みたかったアルゴス市とその周辺が特に印象深かった。そのほか、アテネを中心に荒廃したギリシアの復興に尽力したハドリアヌス帝に改めて興味がわいた。2020/01/11
はる
4
紀元2世紀の人達がみる遺構の数々。先ずはアテネ市内から始まりアゴラ、アクロポリスに祀られた神々や偉人たちの彫刻、墓石、銘文が刻まれた石柱の数々を、恰も地球の歩き方のようなタッチで眺めてゆく。健康な数々の建物、彫刻群を前にしているようだ。アガメノムンの娘イフゲニアに難破遭難者を捧げると考える人々がいる事などに戯曲のネタが日常にあることや、メガラの石像が竪琴の音を奏でた(サヌカイトの様な火成岩が取れたのだろうな)話など、へぇーと思う箇所もあった。遺跡の一つ一つに古代ギリシア都市を確認できる本となったのですね。2025/07/25
刳森伸一
4
2世紀後半のギリシアを巡る旅行記。本書にはアテネを中心とするアッティカ地方に関する第1巻を訳出。単なる名所案内に留まらず、名所に関するエピソードが充実している。特に他では語られることの少ない、マケドニアに支配された後のヘレニズム期の話題が豊富なのが良い。2015/07/04
壱萬参仟縁
3
この辺りもエーゲ海や地中海の荒波で、結構ギザギザな地形であると改めて思える。人名を中心に、かなり固有名詞が出てくるために、何が何だかよくわからない印象だった。経済危機に陥っているのだが、古代哲学者を輩出した地域だけに、残念。前半が本文、後半は注記や解説、年表などから成る。ローマの平和の時代に書かれたという。行ってみたいと思えるか、どうか。エーゲ海からはどんな風景なのだろうか。そんな景色にも興味をもった。遺跡や街道も興味をもったが、行ける場所ではなさそうに思った。世界史を学んだ直後なら行く気にはなるかも。2012/12/21
光莉 レイ
2
純粋に話しを追ってくのたのしい。下巻も、読むと思う。パウサニアスがギリシア全土に旅して、その土地、その場所にまつわる伝承を話していくスタイルで、読者(ぼく)は傾聴する。プラトンの墓がある土地ひとつだって、哲学で聞き知ってた人物なのに一面的にしか見てなかった。こんなにもギリシアという土地と切っても切り離せない、生気のある伝承の中でのストーリーなんだってとても驚いたよ。ギリシアの神話とか、哲学、歴史といった学問をこれから勉強していきたいんだけど、パウサニアスの話しはいつだって学んでいくことの根底にあると思う。2022/05/08