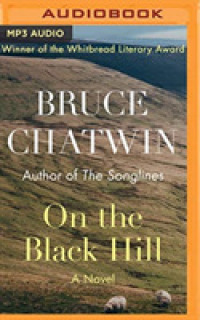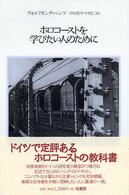出版社内容情報
永平寺の開祖道元が留学を終えて洛南に道場を開いた頃,その学風を慕って参じた懐奘が,日々の師の言葉を録して成った書.勉学の心得はもとより,宗教について死生について等々,人生の根源にかかわる説示もまた,具体的にやさしく述べられている.これらの文言に,読者は,道元その人を感じるであろう. (解説 中村 元)
内容説明
永平寺の開祖道元(1200‐53)が洛南に道場を開いた時、その学風を慕って参じた懐奘(1198‐1280)が、日々に聞く師の言葉を記録したもの。勉学の心得はもとより宗教について死生について等々、人生の根源にかかわる問題が易しく述べられている。忠実な記者の態度を貫いた懐奘の筆によって、道元その人の言葉がよく伝えられているという。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
esop
76
読みづらい!!!! 悟りは居所の善悪にはよらないで、ただ座禅の功の多少にあるべし、らしい。 貞観政要をひいてくるとは思わななかったなぁ。 方便をもって彼れのはらたつまじき様にいうべきなり、らしいよ。 名利を捨てられない人は、道者にもなれないし、正理を得ることもできない! 仏祖の道はただ坐禅なり、とあるように、坐禅をひたすらするというのが道元の教えのようだ。 もっと深めたい。 2025/09/10
藤月はな(灯れ松明の火)
51
フィリップ・K・ディックの処女作、『市に虎声あらん』の解説で「この本が下地になっている」という指摘があります。我欲、地位、財産などの一切を捨てて修行に励む点ではキリスト教の清貧派に似通っているかもしれない。しかし、自分も人も救っていく清貧派に対し、道元は我欲などを修行の妨げとなるものから一切、遠ざけて自分の選んだことに責任を持って貫徹することで自分を救うことができると説く。清貧派の考えは「人も救うことで自分も救われる」とエゴに塗れた曲解になる可能性がある。しかし、道元は「人は人を救えない」と理解した上で2014/09/04
零水亭
30
10代の頃何度も読みました。 既に、この頃の道元禅師、懐奘師の年齢を超えてしまいましたが、これからも読み続けようと思います。2023/06/20
寝落ち6段
23
曹洞宗の開祖・道元の言葉を、弟子がまとめた随聞記。只管打坐、だたひたすら座る、ということを打ち出した道元の人生への考え方や価値観が描かれている。人生にとって本当に必要なものとは何か。物欲や名声欲、承認欲などを捨て去り、最後に自分自身の心に残る自我とはどんなものなのか。そんな本当の自分を見つめなおすために、ひたすら座禅を積む。物が溢れ、忙殺される今の世の中で、心が疲れることが多いと思う。自分自身を見つめるよいきっかけになるかもしれない。本書に「南泉斬猫」への考えも載っていたのが、興味深かった。2023/07/12
零水亭
16
何度読んだのだろう。 当時の道元禅師、懐奘の年齢(30歳台後半)を過ぎてしまってけど、背筋が伸びまする。2024/09/14