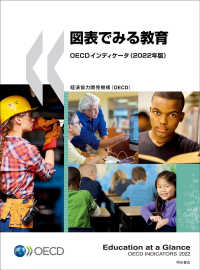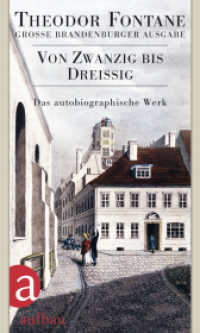出版社内容情報
河童が馬を水中に引きこもうとする――日本各地にあるこの伝説の類話は,朝鮮半島からヨーロッパまで,ユーラシア大陸全域に見られる.この,馬と水神との関係の背後には,農耕社会における牛の役割が潜んでいる.一方で猿と水神の不思議な結びつきが…….時空を超えて人類文化史の復原に挑む,歴史民族学の古典.(解説 田中克彦)
内容説明
水辺の牧にあそぶ馬を河童が水中に引きずりこもうとして失敗するという伝説は、日本の各地に見られる。この類話が、朝鮮半島からヨーロッパの諸地域まで、ユーラシア大陸の全域に存在するという事実は何を意味するのだろうか。水の神と家畜をめぐる伝承から人類文化史の復元に挑んだ、歴史民族学の古典。
目次
第1章 馬と水神
第2章 牛と水神
第3章 猿と水神
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
8
漢字が難読で読みにくい。ルビはあるものの、内容把握が困難。日本以外のフォークロアだから、なのかもしれない。馴染みが薄いためかと思われる。牛と農業は、江戸時代の牛耕とか農具のような知識しか持ち合わせていないので、解説にて「牛と農業」を参照した(むすび241頁)。総括して、ユーラシア大陸全土に分布する水神と牛馬の結合が、儀礼に占めた牛の役割になり、水神への儀礼獣とも(242頁)云々は、なかなか難しそうだが考えさせられる。日本の民俗はなんとかわかるが、世界に拡大されると相関の解明は一筋縄にはいかない感じがした。2013/05/17
うえ
7
解説の田中克彦が抜群に面白い。今日の知識では、著者の挙げる馬の分娩の神の名アジシトではなくアユーストであることを述べつつ、過去の逸話を語る。東大から一橋大学院出講時に、著者と共に人類学の授業を受けた仲間たちには「素性のよろしくない、できそこないの学問だと思っているふしがあって、かれらの先生に対する態度には失礼なところが感じられた」という。人類学→民俗学以上に、言語学→人類学、という蔑視があったわけだ。新興学問は結局のところ、隣接学に認められようとして当初の輝きを喪っていくのだろうか。2021/02/12
シンドバッド
5
本書に引き続き岡正雄の『異人その他』を読むことになるが、本書についていえば、規制がありまた環境が許さなかった状況下で研究され、出版された著者の執念に敬意を表す。2017/07/09
HANA
3
馬、牛、猿と水神の関係について考察。とにかく内容の博学さに圧倒される。世界各国の伝承を集めた読み物としても楽しめた。2010/03/16
志村真幸
2
岩波文庫の1994年に出た新版。解説は、田中克彦。 もともと1948年に出版されたもので、柳田国男の「河童駒引」に対して、国際的な比較民族学の手法を取り入れている。日本だけではなく、中国、インド、イスラーム圏、ヨーロッパ、古代ギリシャなどの例が引かれており、一国民俗学からの決別が明らか。民俗学の成果を国際的に展開させようとした一冊だ。 日本の河童駒引の源流が大陸にあることが示され、牛と馬の家畜文化といつた視点もくみこまれ、おもしろい。 とにかく、無数の例が次々と出てくるあたりが読みどころ。 2024/10/21