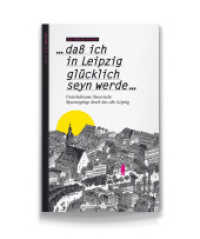出版社内容情報
敗戦後,著者は俘虜としてシベリアで強制労働についた.その四年間の記録である.常に冷静さと人間への信頼とを失わなかった著者の強靭な精神が,苦しみ喘ぐ同胞の姿と共に,ソ連の実像を捉え得た.初版(一九五〇)の序に,渡辺一夫氏は,「制度は人間の賢愚によって生きもし死にもする.それを証明されたように思った」と書いている.
内容説明
敗戦後、著者は俘虜としてシベリアで強制労働についた。その四年間の記録である。常に冷静さと人間への信頼とを失わなかった著者の強靱な精神が、苦しみ喘ぐ同胞の姿とともに、ソ連の実像を捉え得た。
目次
アンガラ河
「どん底」の歌
マルーシャ
「緑の隅」
極光
学校
春
密林の旅
河岸通り
別れ
密林のはてに
懲罰大隊
晩夏
イルクーツク
炭鉱町で
ソヴィエト的人間
ホルスト・ヴェッセルの歌
帰還
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
34
インテリ階級者によるシベリア抑留記。当時のソ連抑留政策は、第1期懐柔期→高学歴インテリスキルを狡猾に利用、第2期増産期→インテリ層に対する下級兵士による下剋上、第3期教育期→ソ連(スターリン)式共産思想洗脳、と時に伴って変化してきている。この変遷が著者の身にまともに降りかかる様が見て取れ、貴重な記録として高価値ながら、そのご苦労を想像すると言葉がない。特に第3期の日本人同志による「反動」闘争は、弱い人間の足の引っ張り合い、人の心の暗黒面があからさまで辛い。1950年芥川賞候補作でベスト・セラー。 2022/10/07
chanvesa
33
著者がソ連側の人間と正々堂々と理論的に意見を述べ、正当な主張をするのに対し、自己批判の集会では身を潜め、みんなで歌ったりせざるを得なかったのはつらかったであろう。谷本の「瘋癲病院にいるあいだはしかたがないさ」(336頁)の言葉が重い。最初の収容所は良い環境(それは周囲の人々を含めて)であったとはいえ、その後の収容所 での身体的精神的な疲労は大変なものであったに違いない。しかし著者が俘虜になってから独学でロシア語を身につけ、改造社で働いていたかなりのインテリであったことから、幾分恵まれていたようにも感じる。2017/09/15
シュシュ
28
『トムは真夜中の庭で』等の児童書の翻訳の高杉一郎さんは、戦後シベリアの収容所に四年間入っていた。収容所を転々とし、その間に出会ったロシア人、日本人俘虜のことが描かれいた。社会主義の『自己批判』という名のつるし上げが怖かった。集団の中では次は自分かもという気持ちがあり、他人のために抗議もできない。高杉さんも黙っているしかなかったが、心の中では茶番だと思っていた。ロシア人は『無差別な友情』を持っていて、俘虜にも気軽に話しかける人が多い。来る人を拒まず受け入れるロシアの民話絵本『てぶくろ』を思い出した。2016/08/02
1.3manen
27
私は慎重に言葉をえらんで答えた。「私はファシズムは嫌いです。それは戦争を準備する機構だからです。それは文化をともなわない権力です」(30頁)。現代ではI AM NOT ABE. 著者は『新約聖書』を耽読した(73頁)という。春:陽気に誘われだしたのか、町の牛たちがアンガラ河の氷の上を向う岸近くまで群をなして散歩に出かけている(113頁)。ソヴィエトの市民生活のなかで愛用されている批判と自己批判(266頁)。 2015/04/16
アナクマ
26
1945年のシベリア俘虜記。巻頭言は鶴見俊輔。わずか80年前のことだが自分にはわからないイデオロギー的背景、まさに黒々と広がる亜寒帯針葉樹林〈タイガ〉に分け入るに等しい。イルクーツク、アンガラ河方面、バアム鉄道。ばらまかれた日本人は5万人。◉著者37才、事務員採用ゆえにロシア人との交流も多いが甘くはない。一方で信頼関係を築けた敵将校もいる。「俘虜生活は大きな学校だよ。誰がほんとうに君の心からの友達であり、誰が見せかけの友達であるかを君は知るだろう。50グラムのパンが…最も親しい友情さえ裂く場合もある」。2025/11/11