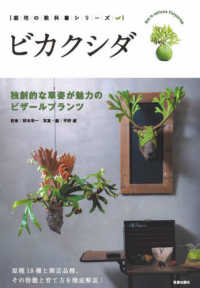出版社内容情報
蝸牛を表わす方言は,京都を中心としてデデムシ→マイマイ→カタツムリ→ツブリ→ナメクジのように日本列島を同心円状に分布する.それはこの語が歴史的に同心円の外側から内側にむかって順次変化してきたからだ,と柳田国男は推定した.すなわちわが国の言語地理学研究に一時期を画した方言周圏論の提唱である. (解説 柴田 武)
内容説明
蝸牛を表す方言は、京都を中心としてデデムシ→マイマイ→カタツムリ→ツブリ→ナメクジのように日本列島を同心円状に分布する。それはこの語が歴史的に同心円の外側から内側にむかって順次変化してきたからだ、と柳田国男(1875‐1962)は推定した。すなわちわが国の言語地理学研究に一時期を画した方言周圏論の提唱である。
目次
言語の時代差と地方差
四つの事実
方言出現の遅速
デンデンムシの領域
童詞と新語発生
二種の蝸牛の唄
方言転訛の誘因
マイマイ領域
その種々なる複合形
蛞蝓と蝸牛
語感の推移
命名は興味から
上代人の誤謬
単純から複雑へ
語音分化
訛語と方言と
東北と西南と
都府生活と言語
物の名と知識
方言周圏論
蝸牛異名分布表
付録
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おMP夫人
12
扱っているのが方言なので音源が欲しいと思うのは欲張りだけれど「蝸牛」という、たったひとつの物を表す単語の方言だけでここまで話が広がるのはやはり面白く、ワクワクします。あくまでこれはほんの一例であり、言葉の伝播・変化に関してこの考察を全てに当てはめる事はできないし、してはいけないのは著者の言うとおり。昭和初期だからこそ、ギリギリ間に合った研究といえるかもしれません。今やっても、ここまでの成果は得られないはず。人の感性によって生まれ、人々の感覚によって変化し、消えていく。やはり言葉は生きた道具だと感じました。2012/08/26
佐倉
10
煙鳥氏が都市伝説のカシマさんを語るのに方言周圏論を引き合いに出していたのをきっかけに読んでみた。文化の中央ほど頻繁に新しい語彙が更新され、辺境ほど古い語彙が残る。その結果、同心円で並べた時、遠くはなれた場所で似た言葉が記録されることがある……という仮説。当時から毀誉褒貶あったようで言い訳がましい語り口も多いが、大学時代の言語学講義で同心円の図を見た覚があるので現代でもある程度有効な説なのだろう。柳田はこの説に関してすっかり萎縮してしまったようだが「アホバカ分布」など実証した話もあるようなので追ってみたい。2022/12/12
かわかみ
6
蝸牛という生き物はカタツムリあるいはマイマイカブリなどと地域によって呼び名が変わる。ところが、近い地域どうしで呼び方が異なるのに、かなり遠くで同じ呼び方をしていることがある。都での呼び方が時代によって変遷すると遠方に伝わるのには時間がかかるので同心円状に同じ呼び名が見られるからという「周圏論」仮説。方言以外の民俗事象にも似た事情が観察されるので柳田の本書によって日本民俗学の方法論として尊重されている。それにしても民俗学には確固たる方法論が乏しい気がする。2024/08/11
でんすけ
3
たくさんの方言の事例を分類し、整理していく。そのあたりの分量の多さと比較すると、方言周圏論に関する主張は少なめ。蝸牛を示す方言は、京都を中心に様々な言葉に移り変わりながら広がって、次々と重なり上書きされていった由。ちょうど川に投げた石ころのつくる波紋のように。言葉の塗り替えは、子どもが操る言葉に由来しているのでは、との発想が面白い。今はテレビがあり、ネットもある。教科書でも言葉の固定化が起こっている。昔ほどのダイナミックな変化はもう起こらないのだろう、少し寂しい。2018/10/19
ちゅん
3
方言周圏論は反証可能性が十分ありますが、作者のフィールドワーク手法は見習いたいところです。2018/10/03