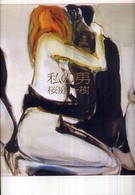出版社内容情報
反幕府の言動により明和事件に連座して刑死した江戸時代の軍学者山県大弐(1725‐1767)の主著.兵書孫子にならって13篇よりなり,正名篇からはじまる.幕府を慮って,自宅水害跡から発見された古書であると後文に記す.「尊王斥覇」を行動によって示すことを強調し,吉田松陰はじめ幕末の志士たちに大きな影響を与えた.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
13
ところどころよくわからないところも。はげしい気魄を感じました。2015/02/19
壱萬参仟縁
10
民衆の窮乏と官僚の腐敗(7頁~)。幕府失政の結果、田野は荒れて穀物はとれないのに、役人はひどい税をかけてくる。これでは国民が窮乏におちいるのも当然である。現代も全く変わっていない、増税の嵐である。漢文の書き下し文理解する以外ない。口語訳は必要だと思える。守業第十では、「農民までが田畑をすてて都市に流れ、末利を逐う生活に堕している」(166頁注)。これは、現代では東京一極集中に繋がっている問題に思えた。持ちつ持たれつの士農工商(40頁)。この作品で頻出するのは、「相輔け相養ひ」(49頁等)である。相互扶助。2013/12/20
こずえ
0
著者は幕末思想家の山県大弐。かなり過激な思想で幕末の攘夷志士たちの思考の潮流がわかる。 特に儒学が絶対的だった時代において放伐論を解釈して幕府打倒を正当化する理由を儒学で完結させた部分はこれが思想家ってやつかと唸った。2018/05/25