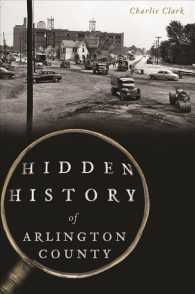出版社内容情報
砂の降りしきる町の娼館「緑の家」、密林の中の尼僧院、インディオの集落など、広大なペルー・アマゾンを舞台に、豊潤な想像力と現実描写で小説の面白さ、醍醐味を十二分に味わわせてくれる、現代ラテンアメリカ文学の傑作。
内容説明
町外れの砂原に建つ“緑の家”、中世を思わせる生活が営まれている密林の中の修道院、石器時代そのままの世界が残るインディオの集落…。豊饒な想像力と現実描写で、小説の面白さ、醍醐味を十二分に味わわせてくれる、現代ラテンアメリカ文学の傑作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nobi
107
アマゾン地方の物語なのに、時々舞台観劇しているような錯覚に囚われる。上手と下手では違った時・場所の違った人物の間の会話が受け渡され、場毎にそれらが入れ替わってゆく。背景は砂塵が舞い蚊が纏わりつき繁茂と腐敗が大手を振るう自然。その自然はインディオと白人の金銭欲性欲を顕わにし暴行への感度を鈍らせてしまうように見える。一つ一つは野卑な会話と行動が多い。にもかかわらず知性が試され想像を掻き立てるような多重の構成と語りの妙。のたうち蠢き煌めく密林の自然に呼応するかのような一幕(上巻)の物語は、二幕(下巻)へと続く。2018/08/23
ヴェネツィア
97
ここまでに随分沢山の人物が登場してくるが、いわゆる主人公というのは、この小説には存在しないようだ。 また、個々の登場人物も、その相互関係を含めてわかりにくい。 読み進めるのには、それなりに忍耐もいったが、それはこの小説が従来の、あるいは我々が思い描く小説の構造とはかなり違ったものだからだろう。 上巻を終えても依然として小説の行方はわからず、混沌としたまま下巻へ。2012/01/12
榊原 香織
86
上下巻の上 時間の観念が消える文体。熱帯雨林の中にいるような。 ペルーの沿岸部とアマゾン。 様々な人間の物語が同時進行、過去の会話と今の会話もごちゃまぜなので、慣れるまで戸惑う(いや、ずっとかな)2024/06/24
NAO
86
【2021年色に繋がる本読書会】ペルーのピウラのスラム街の娼家「緑の家」と、アマゾン川のとある島でインディオの女たちを集めてハーレムを作った日本人フシーアを中心に、いくつもの話が絡み合っている。それらの物語は、過去と現在が混在し、舞台もフシーアの島だったりアマゾン川流域の伝道所がある町サンタ・マリア・デ・ニエバだったりピウラだったりするため、なかなか複雑で分かりにくい。ジャングルの緑、さまざまな人種、未開地の野蛮さ・おおらかさ、等々に、圧倒される。 2021/05/12
キムチ
67
ペルー、ピウラの町、5つの物語が怒涛の如く、だが極めて映画シーン的に同時進行する。リョサの凄さが解りすぎて余りある。読み始めは何の脈絡もない様な会話、呟き、場面描写が時系列を無視してぱっぱっと展開。センテンスが短いから、必至で着いて行く。娼婦の館~緑の家はいわば象徴とでも言おうか・・闇に蠢く様なキリスト教修道院・・のみを取ってやるインディオの娘、いないのにいる振りする修道女と採るふりの娘・・泣かせる。インディオの集落はあたかも石器時代の様相。流れ者が建てた緑の家とその仲間たちが、5本の縄の様に撚りまくられ2020/11/02
-

- 電子書籍
- GOLF TODAY 2024年11月号
-

- 洋書
- Katie John