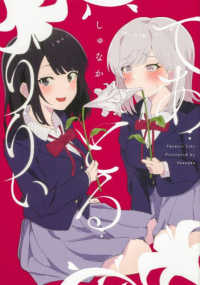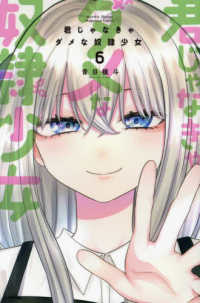内容説明
20世紀スペイン最大の詩人・劇作家ガルシーア・ロルカ(1898‐1936)。表題作に「イェルマ」「ベルナルダ・アルバの家」を加え、彼の最高傑作とされる三つの戯曲を収めた。アンダルシーアという土地の霊と因習がもたらす宿命的な業に苦悩しながらも、他ならぬその苦悩によって浄化されている女たちを描いて「悲劇」の情念がいま甦える。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
297
スペイン内戦のさなかに銃殺されたロルカ。スペインの中の異国とも言うべきアンダルシア。表題作『血の婚礼』は、詩人ロルカの代表的な劇作品である。因習的な地縁と血縁の中で、そして強い光と深い影が交錯する中で行われようとしていた結婚式。劇のプロットそのものはシンプルだし、セリフもけっして多くを語るわけではない。劇の全体を一貫して支配しているのは、どうにもやるせない倦怠感とその先に展望が見えない焦燥感である。そして、アンダルシアの荒涼とした風土感であり、可視的な、また観念的な意味における「血」なのだ。2013/06/23
syaori
60
スペインの詩人ロルカの戯曲三本。スペインといえば太陽と情熱の国というイメージですが、ロルカの描くアンダルシアの何と閉鎖的で鬱屈していること。女たちは夫や家の名誉のために「四囲の壁」に囲まれて暮らし、その欲望も情熱も、夢も希望も悲しみも壁や彼女たちの体に縫いこめられて積もっていくばかり。その積もったものが不意に飛び出して悲劇が起きますが、結局それも再び土地の因習と名誉のなかに沈んでいくと思われるのが何とも言えません。三作どれも壁の中の女たちと、繰り返される悲劇によって大地に撒かれた血の叫びを聞くようでした。2018/10/26
藤月はな(灯れ松明の火)
35
情熱のスペイン女。流浪のカルメンは奔放に生きられたがロルカの戯曲の女たちは地や家、貞淑で家族思いの「女」であることへの期待などに縛られ、その鬱屈が表出するまで溜め込むしかなかった対比が印象的でした。自分の身も心も震わせる男に気づくものの既婚故に軽蔑され、血が流れるまでその結末へ導いた業に気づかない。子供が欲しい女と二人だけの静かな生活を望む夫のエゴの対比が見事な「イェルマ」や家族が子供を縛り付け、憎悪しても帰属せざるを得ない「ベルナルダ・アルバの家」は今も形を変えてある、国や時代が違えども共通する衝撃。2013/06/25
きりぱい
15
スペインと言えば、焼きつける太陽の日差しのような烈しさとは一転、暗いドラマというコントラストが感じられるもするけれど、ここに収められた三篇は最初から光とぼしく陰気。血のたぎりに支配された抑えられない行動が悲劇を招く。血を流させておきながら貞節を誇るだけの花嫁と、まるで宿業のように苦しみをなめる母親が描かれる表題作よりも、我が子を望み思いつめる妻を描いた「イェルマ」や、暴君の母親を始め、5人の娘たちや女中、洗濯女たちと、女の生々しい会話がいい「ベルナルダ・アルバの家」がよかった。2012/10/16
Vakira
13
ガルシーア・ロルカの戯曲3本立て。初ロルカだが これしか知らない。結婚と殺戮てな感じ。実際にあった事件をヒントに物語を作った模様。純愛では無く、実は今後の生活のため、良い人と結婚(愛した人は別にいる)しようとしたため悲劇が起こる。2014/06/18