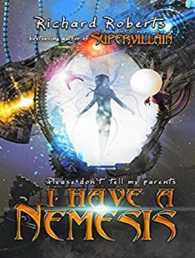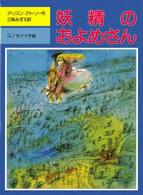出版社内容情報
「いま,近郷夜話を読み終えた.これは素晴しいものだ! これこそ真実の面白さで,とり澄ましたりもったいぶったりしない自然のままの天真爛漫な面白さだ!」プーシキンをして一読三嘆せしめたのが,ゴーゴリ(1809‐1852)のこの処女作集である.これは明るく香わしい小ロシアの田園詩であり,永遠に歌い踊るウクライナ農民の笑いの交響楽である.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ベイス
66
悪魔や妖女がウクライナの豊かな生活の中に溶け込み、正教と異教とが駆け引きを繰り広げる。ゴーゴリのコントのような軽妙な文章、その味わいをあますところなく、いやお釣りが来るくらいかと思われる名訳で味わえる。泉鏡花のようだ。ゴーゴリ初期の作品であまり世に知られていないが、プーシキンが「澄ましたり勿体ぶったりしない真の面白さ」と絶賛しただけのことはある。ウクライナからみた大ロシア、モスクワ、ユダヤ人、トルコ人、ポーランド人観がうかがえるのも興味深い。これを読む限りゴーゴリの故郷はロシアではなくウクライナだ。2025/07/20
syaori
59
「あとからあとから話せ話せで」「もう話には倦きてしまつた!」と語り手のパニコー氏は愚痴りますが、後篇になっても心を惹く物語ばかりなので仕方がありません。相変わらず妖女や魔法使いは日常の中にいて、鍛冶屋の母親は箒に乗って煙突から煙と共にたち昇り、パニコー氏の祖父は悪魔に鼻汁を引っかけられる。人ならぬモノと生活が寄り添っている恐ろしさと楽しさとで背中が「ぞみぞみ」するよう。人が悪魔に一杯食わせたり、食わせられたりする滑稽なものから凄惨で壮大な復讐を詠うものまで、ウクライナの大地から生れ出た物語を堪能しました。2019/08/07
やいっち
27
今朝未明、読了。ゴーゴリの若書きの作品。彼の故郷であるウクライナの、古き風俗や伝説の類いをいかにも彼らしいユーモアタップリに描いている。郷里や郷里の人々愛が感じられる。我々はやがて、「鼻」「外套」「狂人日記」、さらには「死せる魂」「ヴィイ」などを書くに至ることを知っているので、その根っ子、原石を嗅ごうとしがち。取材を重ねて創作したんだろうが、どんどん描き込んでいく作家魂を窺えて楽しい読書体験になった。2018/09/24
fseigojp
24
ドストエフスキーのブラック・ユーモアはETホフマンの影響が有名だが、ここにも源流があるかもしれない 2017/11/07
Ribes triste
17
お人よしで、勇猛果敢なコサックたちが大活躍する短編集。挿絵入りなのも嬉しい。悪魔は全く違う生き物だけも、人に害なす妖女や魔法使いの家族は、いたって普通の人でだったりするという設定が面白い。それにしても、こ続々と出てくるロシア料理の名前が美味しそう。2019/05/25