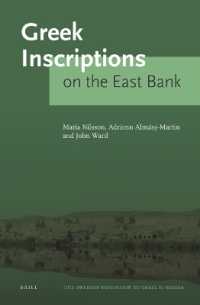出版社内容情報
この小説は西洋の芸術家が,東洋精神への目ざめと傾倒との過程を描いたものである.インフレ時代にベルリンのある音楽家夫妻が窮乏のために日本のナカムラなる教授に間貸しをすることから端を発し,やがて日本人への理解,象徴的神秘的な東洋芸術や仏教思想への憧憬に進んでゆく.解説=成瀬無極
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アトレーユ
8
うん〜…起承転結でいうと転句まではとてもいいのだが、最後のまとめ方がなんだかなぁ…彼方では人がバタバタ死んでいく一方で、此方ではのんびり森を散歩している。そこに無常観を感じる、というのは新しい視点だった。それはとても素敵な感覚なのだが、でもこのまとめ方はなんだかなぁ…2024/06/01
ひでお
4
第一次世界大戦後の日本というのはお金持ちとみなされていたのかな。敗戦国のドイツから見たらそういう感じだったのかも。成り上がりの東洋人という偏見から、いきなり日本崇拝に転換するストーリーはかなり苦しいし、関東大震災の描き方も誇張しすぎ。ここで描かれているのが仏教思想かというとそうとも思えないし。なんとなく消化不良の読了でした。しかし巻末にある、本書の「ナカムラ」のモデルと言われている人の解説が、一番おもしろかったかも。2021/07/17
Nemorální lid
4
『人を魅するばかり軽妙慧眼の芸術たるが故のみならず、その人間味の故に』(p.4)優れている、とツヴァイクが述べた当著の中の『懊悩と焦燥』(解 p.3)が如何に"日本人"を通じて変化していくか、という観方から読んでみると、東洋と西洋の違いというのが鮮明に分かる。最後は『苦悩が屈辱であると思うのは、それは独逸的、欧羅巴的の誤謬であった』(p.117)と仏教的無常観のフィルターを介して描かれており、主人公達の感情の変遷と日本人との邂逅が『仏教的苦悩をテーマとする教会用交声曲』(解 p.4)を大成させたと考える。2019/01/31
遠藤三春
2
タイトルが気になって。ルードルフのツンデレかまってちゃんぷりが可笑しかった。段々日本人「ナカムラ」や彼らの信仰、思想に惹かれていく。解説では、モデルになったのではと思われている成瀬無極が、冒頭は訳者の相良守峯が。相良さんの序文が、この少し理解しがたい本文をきれいに説明してくれていると思う。しかし関東大震災の様子が、小説だとゴジラ襲来的世紀末さが感じられてやばい。面白かった。2013/05/09
天動火茶遠
1
旧仮名遣いの文章を読むのも久々なので、慣れるまで数ページかかった。この本の醍醐味は翻訳者の序文、作者の本文、解説者の解説文を同時に読めるということにあると思う。特に解説は学者らしい論理的で明快な文章でとても面白い。もちろん本文も面白い。「これはフィクションです。実在の云々」という定型文を頭に叩き込んで読んでも、そこここで思わずツッコミを入れてしまいました。2012/07/24