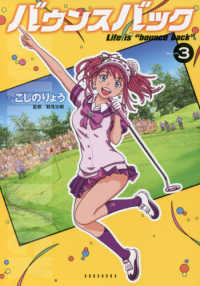出版社内容情報
全十篇の完成に実に十年もの歳月を要した『ドゥイノの悲歌』(1923年)は、『オルフォイスに寄せるソネット』と並ぶ、リルケ(1875-1926)畢生の大作である。作品の理解を深めるための詳細な註解を付す。
内容説明
『ドゥイノの悲歌』は、『オルフォイスに寄せるソネット』と並ぶリルケ(1875‐1926)畢生の大作である。「ああ、いかにわたしが叫んだとて、いかなる天使がはるかの高みからそれを聞こうぞ?」と書き始められた調べの高いこの悲歌は、全10篇の完成に実に10年もの歳月を要した。作品の理解を深めるための詳細な註解を付す。
目次
第一の悲歌
第二の悲歌
第三の悲歌
第四の悲歌
第五の悲歌
第六の悲歌
第七の悲歌
第八の悲歌
第九の悲歌
第十の悲歌
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
106
リルケの散文詩のような感じの作品です。注釈と解説が半分以上を占めています。それだけに難しいのかもしれません。私も一回読んだくらいではわからないので、この10の散文詩をじっくりと読みました。最初は註釈も見ないで次は註釈を参考にしながら読みました。また解説のこの作品が書かれた背景などを読むと少しわかる気がしました。第九の悲歌が私には印象深く思われました。2022/11/19
lily
92
肌と肌の触れ合いは幸せの素の強力磁石。ベクトルを変えて、くっついたり弾いたりしながら、どこかには確かにある愛の砂鉄を目印に彷徨う。磁力線の消し方は分からない。人間だもの。体温と湿度と柔らかさと凹凸を持ってしまったもので。2021/05/03
NAO
86
再読。これもまた『マチネの終わりに』で言及されていた、リルケの思想詩。1911年から翌年にかけて、タクシス侯爵夫妻の誘いで訪れたドゥイノでリルケが霊感を受け、書き続けられた10の悲歌は、最初は不安な存在にさらされてている人間の惨めさと苦悩が歌われているが、徐々に最初の方の否定的な考え方から、人間の存在の意味を見出しそれを肯定する方向へもっていこうとするリルケの意図が強く感じられるようになっていく。その道筋の間には、どれほどの思いがあったことだろう。これは、その思考の流れを刻々と歌った思想詩なのだ。2019/05/12
新地学@児童書病発動中
80
リルケの代表作の一つ。生や死、宗教、芸術、恋愛など人間にまつわる全てのことがここで表現されている。この世を超えた世界への憧れを歌いながら、この世で生きていく決意が表明される第9の悲歌は詩という芸術の頂点に立つもの。苦しみもがきつつ生きる人間に対するリルケの優しさを感じる。美は天上のものではなくこの世界で見出せるという想いはリルケが詩作を通して得たものだろう。難解だが、イメージの展開の仕方はたくみで、じっくり読めば注にそれほど頼らすに詩の世界に入り込めると思う。手塚富雄氏の訳は格調が高く読みやすい。2013/07/05
syaori
78
詩を読みつけない者には難解で、註解に大いに助けられました。それでもこの詩に魅了されたのは、「われらは消えゆく」、人の記憶の「うちより、またほとりより」と移ろう身や世を嘆いていた詩人が、その怖れや儚さを見つめたうえで「この世にあることはすばらしい」と力強く謳うからなのだと思います。なぜ「生を負い」続けるのか、それは「幸福があるからではない」と詩人は言う。天上の「美」に憧れながらも、歎きに満ちた、ただ一度の地上の営みを見つめ感受し、それにより遥かな星々に至るのだと歌うその声に心奪われずにはいられませんでした。2019/10/01
-
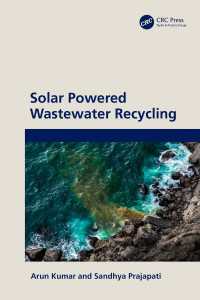
- 洋書電子書籍
- Solar Powered Waste…
-

- 電子書籍
- フードビズ85号