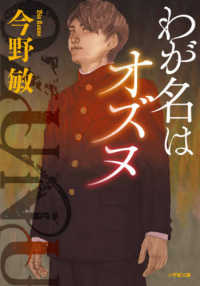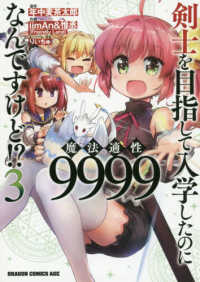出版社内容情報
本当のジェントルマンを作り上げるための全人的教育制度をもって誇るパブリック・スクールの生活が作者(1822‐1896)自身の体験に基づいていきいきと描かれている.そしてこの教育の成果は,本篇の主人公トム・ブラウンの成長の過程が雄弁に物語る.少年社会のあふれるユーモアと,底を流れるキリスト教精神と,スポーツ精神の調和が高い香りを放っている名作.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
116
イギリスのパブリックスクールのようなところでは、校長を始めとする学校のあり方と、どういった級友と過ごすかということが、少年たちの人格形成にどれほどの影響を及ぼすものかがよくわかる。日本では家庭の役割も大きい。イギリスでは、寄宿学校に入るまでの親との関わりの仕方もまた違うのだろう。終盤のトムと先生との話しに出た「ただ労働して糧を得る事だけを考えて働くと金儲けの方ばかりに心がいく。社会のためになることを考えるために大学に行く」という考えは大変立派だが、それはやはり階級社会的考えが潜んでいるとも思えた。2016/12/12
watson
4
本来なら他の生徒に良い感化を及ぼしうるトムだが、苛烈すぎる正義感の裏返しから反抗を重ねて放校寸前、というのが先学期まで。校長の配慮により、虚弱ながら牧師の亡父譲りの信仰心と知性に溢れるアーサーと同室になると、互いの不足を補いあううちに人間的成長を遂げる。人生は学校を卒業してからのほうがずっと長く、その間いかに辛くとも学寮生活を思い出せば大抵のことは耐えられる、という。つまり、その非人間性と、人格が陶冶される過程の喜び、という二つの思い出の為に。2016/09/29
1.3manen
3
「吾人は、死が無限の祝福となるやうな生き方とはどんな生き方であるか、また生きてゐるよりも、むしろ生れて来なかった方がましだったと思はれる生き方が、どういふ生き方であるか」(116ページ)ということは、なかなか意義深い指摘だと思った。前者は金子哲雄氏のように生前に遺書を書いて亡くなってから出版する行為。後者は世間の迷惑になる行為全般かと思える。「君は自分の職業で大変に結構な暮しができてゐながら、世間の為になることをちっともしてゐないで、かえって大変に害を及ぼしてゐる場合もあるのだよ」(190ページ)。然り。2013/02/08
madhatter
0
下巻では、上巻末尾でアーノルドの蒔いた種が芽生え、成長してゆく。アーサーとの出会いによってトムが成長してゆく過程は、現代でもある程度通用する普遍性を持っているように思われる。また、アーノルドに対するトムの尊敬の念には、時代や宗教を超えた感動がある。教育理念や、それに基づくヒューズのお説教が些か古臭かったり、宗教・風俗の違いで違和感を覚えはする。また、ヒューズの書き方に、大人の理想の押し付けを感じ、不満がなかった訳ではない。しかし、下巻を読んで、それを超えた何かが確実に残る作品ではないかと考えを改めた。 2010/03/09
takeakisky
0
始めの頃の少し皮肉を混ぜた書きぶりが少し懐かしくなるくらい、真っ当。小っ恥づかしくなるほど、真っ当。一部で娯楽ものとしていた認識を改め、教訓ものだな、と。そしてトム・ブラウンとその成長を描きつつ、実は、彼らの如き英国青年を作り上げた校長アーノルドこそ影の主人公。リットン・ストレイチーもヴィクトリア朝偉人伝で評伝を残したアーノルド博士。確かストレイチーは前時代的で悪しきパブリックスクールを作った元凶みたいに書いていた記憶がある。この人オルダス・ハクスリーのひいおじいちゃんらしい。ネタとして覚えておこっと。2023/05/31