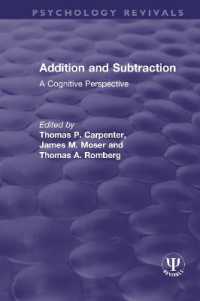内容説明
ベトナムで聞いた迫撃砲の轟音、死体が発する叫びと囁き、アマゾンで鳴り響くベートーヴェン―。記憶の中の“音”をたよりに半生を再構築し、精緻玲瓏の文体で綴る散文詩のような自伝『耳の物語』の後篇。芥川賞を受賞して作家となり、ベトナム戦争を生き抜き晩年にいたるまで、滔々と流れる茫洋たる過去を耳の記憶で溯る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いのふみ
3
「私」という語を使わず、自分を語るという手法が伝統的なものだったとは知らなかった。壽屋時代が仕事や同僚など、社会の喧騒に塗れながらも愉快に感じられるほどであるのに対して、作家専業時代は別人のような陰鬱さを感じた。何かに追い立てられているような焦燥も感じた。2019/09/15
さえもん
2
心は捉えようがなく捉えようとすると崩れてしまう。それを崩さずに言葉で表現しようとする。でも、言葉で表現しようとすると固定されてしまう。その苦闘が開高健の文章からは読み取れる。人間はこの苦闘を続けていくのだと思う。 初めて聴く音楽で鳥肌が立つ、でも、そのあとで何回聴いても初回のような圧倒された感じを体験することはできない。著者も同じような体験をしていて何か嬉しい感じがした。2022/11/26
chiro
2
開高健の自伝の後編。氏が作家として歩み始めてからの物語は物書きとして在る事に呻吟する姿が詳らかにされていて、内面を描く筆においても氏の表現力の強さ、確かさを感じた。氏がアイヒマンの裁判を傍聴していたのは驚いたが、氏が語るアイヒマンはアーレントが語った凡庸さを裏書きするものでむしろその凡庸さを際立てていた。最後にモーツァルトを通じて音楽の一回性に言及しているが、エリックドルフィーも同じことを語っておりなるほどと感じ入った。2019/06/07
mooroom7
1
青い月い曜日を読んだら、解説の池澤さんが、これも読むよろしと言っていたので。2巻から読み始めてしもうたが。過度な文飾をどう受け止めるかは読み手のコンディションによる。今回「闇」よりも強く撃たれることはなかったなあ。むしろ、開高旦那が作家として開始する契機や経緯が詳らかであって、興味深い。才能の塊のように思える存在の内面は、呻吟苦吟の苦闘が当然でもあるのか。誰かが締め切りさえ設定してくれれば俺にも傑作が書けるのかも。なんて思わせるなあ。60年に満たなかった生涯をこんなにも濃密に生きることができた。裏山でも。2025/03/28
大臣ぐサン
1
性表現が下卑ていて気持ち悪くてやだな。2022/07/23