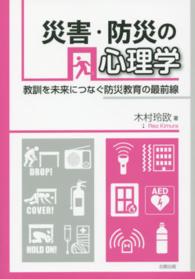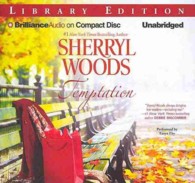出版社内容情報
「私にとっては寧ろ解釈することが創作する事の様にすら感じられる。」学者にして詩人、ともに比類ない業績をのこした折口信夫が生涯その中核においた歌。遥かに見透しまた限りなく近く、鋭敏な眼は三十一文字に沈潜し読みひらく。「叙景詩の発生」「隠者文学から女房文学へ」など様々な視角から論じた全13編を収録、注を付す。
内容説明
「私にとっては寧ろ解釈することが創作する事の様にすら感じられる。」国文学者・民俗学者にして歌人・詩人、比類ない業績をのこした折口信夫(1887‐1953)。学問と創作との双方を、「うた」がつらぬく―「叙景詩の発生」「女房文学から隠者文学へ」など、文学史を構想し、一首を読みぬく「折口学」の精髄13篇を収録。注を付す。
目次
叙景詩の発生
短歌本質成立の時代―万葉集以後の歌風の見わたし
女房文学から隠者文学へ―後期王朝文学史
古歌新釈
古代民謡の研究―その外輪に沿うて
古代民謡の研究
難解歌の研究
誹諧歌の研究
誹諧の発生―農村に於けるかけあい歌
山の音を聴きながら(東歌抄)
文学に於ける虚構
評価の反省
詩歴一通―私の詩作について
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
11
ボリュームのある詩歌論集。編者の註釈が理解を助ける…が、編者自身は「疑念や混乱やを新たに書き立てる結果となろう」としているのが面白い。「私も以前は、旅の途すがら、海原を見晴し、美しい花野の展けて居る場所に来た旅人たちが、景色にうたれて、歌を詠じたものと考えて居た。併しそれは単なる空想であった」「私は人麻呂が支那の詩の影響を受けて、対句・畳句その他の修辞法を応用したという様な考えは、もう旧説として棄ててよいと思うて居る」「奈良の詞人の才能は、短歌に向うてばかり、益伸びて行った。長歌は真の残骸である」2017/11/25
roughfractus02
6
国文学の発生の基点を超自然的存在とのコミュニケーションとし、『万葉集』を「鎮魂」歌集と捉える著者の詩歌の史的展開を辿ると、古代の「鎮魂」の言霊的な力が自己の内を瞑想する力に変容する傾向が読み取れる。その一方で、民俗学的見地から著者は、階級内の交流が主な貴族階級の外に出る詠み手が増え(「女房文学から隠者文学へ」)、詩は武士や農民や山の民が生活する習慣や景観を取り込み、詩形式も貴族以外の民衆の歌の掛け合い等と混ざり合い、和歌から俳諧へと変容するという見解も提示する(「俳諧の発生――農村に於けるかけあい歌」)。2025/03/27
toiwata
5
説得されるのだが、なぜその結論に至ったのかがわからない。本人の中では論理的な道筋が必ずあるはずである。しかしそれが省略されているように見える。たとえばこの一節。”日本の歌に、難解歌でないものが、果たして幾首ありましょう。” (p. 237 「難解歌の研究」)2018/01/19
壱萬参仟縁
4
山の音を聴きながら(297ページ~)。「幽かな音である。立ちどまって聴くと、耳を疑うばかりの静けさを、山の中に感じた」。山の民である評者も、静けさを確保されない場合は田舎らしさはなくなりつつあるのを残念に思っている。また、大伴家持が40歳の時の歌について、「しみじみと昔の人をうらやましく思うのは、自分の生きている時代が、昔と大きく変ったと言う事を考える時である」(326ページ)。特に、原発事故以来、なんとかならないものかと。詩歌の分析というとき、現代人は感性が鈍っているので自分なりの解釈が求められるなぁ。2013/01/18
十一
2
理知により言葉を研ぎ澄まし、未だ語られぬものに届かんとする2014/07/08