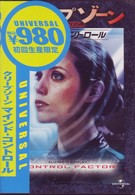出版社内容情報
「した した した。」雫のつたう暗闇で目覚める『死者』。「おれはまだ、お前を思い続けて居たぞ。」古代を舞台に、折口が織り上げる比類ない言語世界は読む者の肌近く幻惑する。同題の草稿2篇、小説第1作「口ぶえ」を併録。
内容説明
「したしたした。」雫のつたう暗闇で目覚める「死者」。「おれはまだ、お前を思い続けて居たぞ。」古代を舞台に、折口信夫が織り上げる比類ない言語世界は読む者の肌近く幻惑する。同題をもつ草稿二篇、少年の日の眼差しを瑞瑞しく描く小説第一作「口ぶえ」を併録。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
84
(前略)しかし、人は生きる。愛される少年の時も過去となる。自分を全否定するか。それとも、肯定する道はあるのか。そこに古代史の世界がまざまざと立ち現れてくるのだ。どのような愛の形も赤裸々に表現されている世界として。しかも、現代の狭い了見の性道徳からは倒錯しているという言い方でしか捉えられない世界に<美>の極が示されている。現世の窮屈な道徳など、古代より連綿として続いてきた宮中を中心とする愛欲と手練手管の世界からしたら笑止に過ぎない…。(後略)2006/07/31
えりか
49
「死者の書」した、した、したと垂れる水音。つた、つた、つたと響く足音。想いを残し甦る死者。夢かうつつか、この忍び寄る幻想がたまらない。ぞっとする妖しさ。郎女の命を込めて描ききった曼陀羅が目に浮かぶ。時間軸の交錯と慣れない文体に途中何度も読み直したが、素晴らしかった。「口ぶえ」同性愛に悩む15歳の青年。倦怠感しかない。私小説ということでその死生観が色濃く伝わる。「死にたい」わけではなさそうなのに、「いつ死んでもいい」という感じ。生への執着が皆無のよう。この暗く静かな文体が心に入り込んでくる。未完なのが残念。2017/11/05
アキ・ラメーテ
44
独特のオノマトペ(した、した、した。、のくっと起き直ろう等)もいい。むずかしいと思って、気になりつつも敬遠していたけれど、ふりがなや注解がたっぷりで思っていたよりもわかりやすい。美しい日本語に、ほぅっとなりながら読んでいた。残念なのは『死者の書 続編』と『口ぶえ』が途中までであること。2015/10/05
井月 奎(いづき けい)
37
非常に長いレヴューになりましたので、下記のコミュニティに投稿しております。よろしければお読みくださいまし。https://bookmeter.com/communities/3368032020/01/13
chanvesa
36
「死者の書」は折口信夫が追求していた民俗学の死から、さらに普遍的な死を描いたように思う。死と向かい合う一人の人間としての朗女と、ラストの彩画(曼荼羅)の想像させる美しさ。但し場面が前後するので難解だし、今でも斬新。「口ぶえ」の少年愛は彼自身の思いもあると思うが、彼の少女的な趣味や純粋さが前面に出ている気がする。「口ぶえ」の叔母さんの言葉、「苦しみに来た世界やもん、でけるだけ苦しんどいたら、末はどないなとなるやろおもいまひてな、この頃ではちょっとでも間があると、六条さまへおまいりいたしあす。」の素朴な信仰。2018/01/29
-

- 電子書籍
- 宇宙商人16【タテヨミ】 Studio…
-

- 電子書籍
- 【電子版限定作品あり】nanahosh…