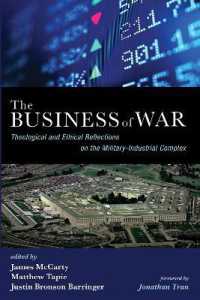内容説明
木曾の旧家に生まれ、古い「家」の崩壊を体験した島崎藤村(1872‐1943)の自伝的作品。封建的な色彩を色濃くのこしている信州の二つの旧家、小泉家と橋本家。この家父長制的な「家」の下に生きてきた大家族数十人の人々の個々の運命を描くことによって、古い「家」の頽廃と崩壊の跡をたどる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
カブトムシ
21
島崎藤村の明治31年から明治43年にいたる13年間の自伝小説である。主人公の小泉三吉を中心とするけれど、姉お種の嫁している橋本家(高瀬家)と小泉家(島崎家)との「二大家族の家長達の運命」を追求し、明確な構造を持っている。次に「家」の題意は、正太(お種の息子)や三吉を中心とする「新しい家」の意味がある。三吉は暗い家を離れ、お雪を妻に、小諸に行って田舎教師になった。正太も結婚して新しい家をつくる。自然主義的リアリズムの最高傑作として正宗白鳥にも広津和郎にも評価された。私は、山寺宏一さんの朗読を数度聴いた。
あかつや
8
小泉家と橋本家という姻戚関係にある2つの家族を描いた物語。どうやらこの旧家が没落していくらしい。家長がどうも山っ気があるようで、なにやら怪しげな商売に手を出していたり、女性関係が色々ややこしかったりと、家庭の問題が次々と起こってくる。上下巻合わせてもたいしたページ数ではないのにやたらと登場人物がいて、それぞれに何かしらの問題があったり、その問題ももっと深く書かれてもよさそうなのに、さらっと時が経過していつの間にか片付いていたりでどうも目まぐるしい。でもこの目まぐるしさがちょうどいいんだなあ。下巻も楽しみ。2019/07/01
ゆか@nya
1
★★★★☆2015/04/06
愁
1
家になにかしらの問題の無い方は少ないと思います。時代は違いますが、同じ様な境遇だと興味深く読める所が多そうですね。個人的には、何カ所か考えさせられる部分がありました。内容の理解には他の藤村作品との併読も必要ですね。2015/02/22
kumiko
1
大学時代に読んだのを再読。カタカナ混じりだったり、方言だったり、今とちがう、当時の表現がおもしろい。2014/05/14