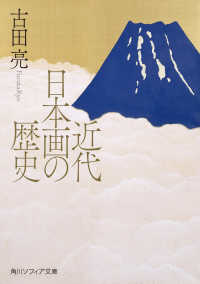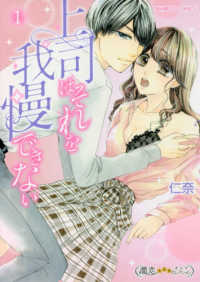出版社内容情報
円朝はこの話を作る時,塩原多助の遺跡のある群馬県までわざわざ実地に山越しするなどして苦心を重ねたといわれる.炭屋塩原多助が貧から身を起こす立志美談であるが,とりわけ愛馬青との別れは満場の涙をさそう熱演であったと伝えられている.歌舞伎上演はもちろん,明治帝の御前口演,小学校の教科書採用など多くの逸話も残っている.解説=正岡容
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
望月衣塑子そっくりおじさん・寺
62
先日、脚本家の笠原和夫の『昭和の劇』を読んで大変面白かったのだが、笠原さんが脚本家になるにあたってマキノ雅弘監督に「脚本家になるなら仮名手本忠臣蔵と円朝は読んでおけ」と言われたとあった。その前に読んだ小倉鉄樹『おれの師匠 山岡鉄舟正伝』に、鉄舟に鍛えられた円朝の話があった事もシンクロして、本書を読む事にした。かつて『牡丹燈籠』は読んだが、私は怪談に関心が乏しい為、強い印象を覚えなかったが、上毛カルタに今も詠まれる塩原多助のこの物語、面白過ぎるではないか!。運命に翻弄され善が悪になるダイナミズムが話芸で!。2019/04/07
駄目男
14
怪談噺を得意とした初代三遊亭圓朝が明治九年から書き始め、十一年に完成した実在の塩原太助をモデルにした立身出世物語。二十四年、井上馨邸において、作者自身により明治天皇の前で口演されたらしい。然しこの本、注釈がないのが恐れ入る。書かれた当時の原文のままで、古書店で初めて見た時、ぺらぺら捲って見るに改行なしの細かい字に恐れおののいてしまうほどだったが、あとは闘争心ですね。読んで読めないことはないと読み始めるに、これが意外とすらすら読めて面白い。言文一致運動にも大きな影響を及ぼした『牡丹燈籠』も読んでみようかな。2025/01/22
猫丸
1
群馬県民には、お馴染みの塩原多助。
koishikawa85
1
立身出世譚だからある程度はパターン化しているのだが、それでもぐいぐいひきつけられる。驚いたのが途中までまともだったはずの妻と姑が養父が死んでから急に大悪人になって多助を殺そうとするところ。2015/06/22
gen
0
旧仮名遣い、旧漢字に苦闘しながら何とか読了。 人情噺圓朝を堪能でき、前半の辛かった多助の運命がラストのクライマックスで漸く、報われカタルシスが有った。2016/01/26