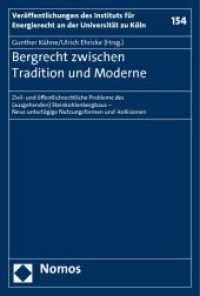出版社内容情報
旗本のひとり娘お露の死霊が,燈籠を提げカランコロンと駒下駄を鳴らして恋人新三郎のもとに通うという有名な怪異談を,名人円朝(1839-1900)の口演そのままに伝える.改版.(解説=奥野信太郎/注=横山泰子)
内容説明
旗本の娘お露の死霊が、灯篭を提げカランコロンと下駄を鳴らして恋人新三郎のもとに通うという有名な怪異談を、名人円朝の口演そのままに伝える。人情噺に長じた三遊亭円朝が、「伽婢子」中にある一篇に、天保年間牛込の旗本の家に起こった事実譚を加えて創作した。改版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
102
生者と亡者の恋物語を哀しくも美化した作品でした。怖さよりも哀しさが優ります。結局、新三郎はどうすれば良かったのでしょうか?作品の結末で新三郎はきっと満足だったに違いないとは思いますが、それは新三郎の「弱さ」なのでしょうか。しかし、そこに「強さ」は必要なのでしょうか。そんなことを考えさせられた作品でした。2023/06/15
アナーキー靴下
72
カランコロンと下駄を鳴らし現れる美しい死霊との夜な夜なの逢瀬、という怪談話としか知らなかったけれど、元々は落語で、不義に仇討ちにと様々な思惑入り乱れる人情噺の一部として怪異談が花を添えている感じ。感情もあらわに善人悪人激しくぶつかり合う様はシェイクスピアのようにドラマチック。でもシェイクスピアの場合、善悪は他人次第、最終的な審判は神である、と感じるけれど、本作の場合、善悪は己の行為によって体現すべきもの、と感じる。社会的な自治を己に課しているような。義理人情に厚いが自らの規範を逸脱することもないのは凄い。2023/08/09
goro@the_booby
66
円朝の怪談話を速記し本にまとめたものだが、これだけ長い話を何回に分けて高座に掛けたのでしょうかね。牡丹灯籠の幽霊話かと思ってたけどこれは遠大な因果応報の物語。幽霊話は本題と言うより脇のお話で、お露の父である平左衛門を巡る物語の輪の中の一つだった。出てくる人物がグルグル繋がってドラマが廻って行く展開が凄い。円朝さんが物書きになってたらと思うと妄想は尽きないが、こうやって残ったのが奇跡。残さなきゃいけないと当時の人も考えたんだろね。いつの世も人は変わらないやね。2022/08/11
NAO
63
明治時代の落語家三遊亭円朝が、『伽婢子』の中にある一遍に、天保年間の牛込旗本の家に起こった事実譚を加えて新たに創作した怪談落語。幽霊が登場する怪談であるだけでなく、後妻と間男の主人殺し、敵討ちと話は盛りだくさんで、落語というよりは講談といった感じ。一方では、美しいお露の死霊が恋人を求めて夜をさまよい、一方ではあくどい女と情夫が夫を殺そうと毒牙をむき出しにしている。人間のあまりにも醜くどろどろとした欲が渦巻く中、だからこそ死霊お露のぞっとするほどの美しさが際立つ。目で読むより耳で聞く方が怖さが募りそう。2016/08/06
姉勤
45
6代圓生をはじめ、噺家の腕を量る怪談話として知られる牡丹灯籠。高座では、焦がれ死にしたお露にとり殺される新三郎の怪異を主体とした場面が演られるが、円朝作オリジナルは多重な人間関係と因縁、怨恨が折り重なったレイヤーを呈しており、金銭欲や色欲、怨恨を晴らしたい人間的業にまつわる話と、主君への忠誠、敵討ち、仏教説話など勧善懲悪の話が交じり合っている、落語として残るのは前者の部分。大胆に削り組み替えているが、見事に編集された作品になっている。「通し」で演られる牡丹灯籠と違う筋を、まだ何本も噺が取れる、円朝の天才。2019/01/08