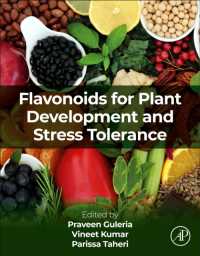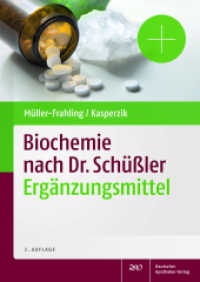出版社内容情報
日本人に愛唱されてきた歌謡は,時代により様々である。特に、近世末期から明治初期を絶頂期とした民衆による流行歌曲「端唄」は,日本歌謡史上,逸することが出来ない.三味線を伴奏にして、恋のやり取り,郷土の風物への思い,世相・政治への風刺が,哀切、粋な調べにのせて詠われる.爛熟,洗練された近世文化の最後の精華を伝える代表的な端唄を,初めて編纂する.
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
32
38 雪はしんしん 雪はしん〜 夜もそのとふり どふせ こまいと まんなかへ ひとり ころりと ひぢまくら 何どきじや アヽ寝(ねい)られぬ(40頁)。78 一条戻橋 一条今出川 二条のきぐすりや 三条のみすやばりに 四条の芝居 五条のはしべんけいに 六条のほんぐわんじ 七条のそうばみせに 八条の小べんとり 九条の竹の子ほり とうじの らしやうもん(94頁~)。烏丸五条交差点はよく右折します。倉田喜弘氏の解説によると、端唄の演奏時間は平均1曲3分ですぐに口ずさめるとのこと(229頁)。2014/12/28
スローリーダー
2
江戸時代の音楽環境はこんにちとはかけ離れていた。今の我々が、西洋音楽の姿も形も概念も無い世の中を想像することは難しい。西洋音楽がほぼほぼ存在しない(シナ、ポルトガル辺りの音楽はあったかも)江戸を前提として端唄などの邦楽を理解すると、これらの芸術性の高さとか文化度の高さとか庶民の娯楽としてのエンタメ性の高さとかがにわかに見えてくる。百人一首を本歌取りした都々逸の遊び心が粋だ。端唄百番の内8割方は曲が聴けたけど俗謡·都々逸の多くは録音が見つからず、調子を知ることが出来なかった。2023/03/01
大臣ぐサン
1
江戸時代末期に流行した端唄、俗謡、都々逸等を収録。 「半髪頭をたたいてみれば 因循姑息の音がする 惣髪頭をたたいてみれば 王政復古の音がする ジヤンギリ頭をたたいてみれば 文明開化の音がする」 これは都々逸。2019/02/16
tnk
0
地歌の歌詞と比べて、主題も口調もだいぶ俗である。地歌は地歌で好きだが、端唄には当時の人々の息遣いをより感じる。2015/11/04
-
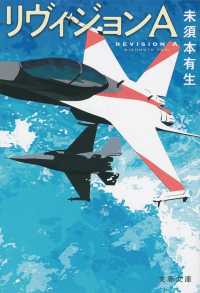
- 和書
- リヴィジョンA 文春文庫