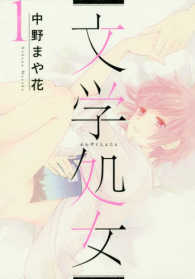出版社内容情報
『日本外史』(全二二巻)は,その対象を頼山陽の生きた武家時代にとり,平氏から徳川氏に至る漢文体の通史である.記述の範を司馬遷『史記』の「世家」にとったが,その巧妙な叙述は「穏当にしてその中道を得るが故に,朕兆(きざし)の眼に見えざることまでも逃すことなし」(松平定信)といわれ,とりわけその人物描写に生彩を放つ.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
17
◎日本外史の中でも特に好きな巻です。とはいいながらも一気に読むことは出来ずじわりじわりと隙を見て読んでいました。特に毛利と織田の部分が好きです。後北条の部分で勝頼が氏政の妹をよめにしたことをもって配下になったと言う話等ところどころ驚かされる部分もあります。2020/10/04
零水亭
9
①武田氏・上杉氏の巻が特に好きです。 ②足利氏の「論賛」が痛烈ですね💦2025/02/09
アメヲトコ
4
中巻は足利氏から後北條・武田・上杉・毛利氏、そして織田信長まで。ところどころ史実と異なる話が出てくるのはご愛敬でしょうか。毛利氏への論賛では山陽の安芸人としてのプライドが垣間見えます。2016/11/26
denz
4
「足利氏」「後北条氏」「武田氏・上杉氏」「毛利氏」「織田氏」を収録。やはり面白いのは、「超世の才」を示した「織田氏」。彼の残虐な殲滅戦の前には、必ず重臣が戦死しており、その復讐という様相を呈している。信長は、内と外の感覚が明敏な「友敵」論の「政治」家だったようだ。また、完全に失墜していた「王室」が、信長の登場によって急上昇する。これが山陽の考える徳川体制の基礎をつくったという認識だろう。ちなみに本能寺の変の原因は、「怨恨」に求めている。本書が日本人の歴史観に与えた影響力は多大だと改めて思う。2012/02/26
Ohe Hiroyuki
3
中巻は、足利氏に始まり、織田氏まで収録されている(7巻~14巻)▼足利氏の諭賛はなかなか刺激的である。「源氏は王土をぬすみ」「足利氏は王土を奪い」である。日本外史のスタンスを強く感じるところである。▼本書では、色々な氏の者が外史が収録されているが、戦国武将を孫子・呉子の使い手と評したり、孫堅のようだと論ずるところは、親しみを覚える読者もいるのではないだろうか。▼なお、毛利氏までは足利氏後記であり、織田氏は徳川氏前記である。織田氏序論において封建を論ずる部分があり、歴史を考えるうえで大いに参考となる。2025/10/09
-

- 電子書籍
- ルドルフ・ターキー【分冊版】 39 H…
-
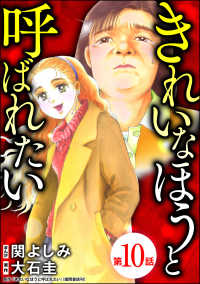
- 電子書籍
- きれいなほうと呼ばれたい(分冊版) 【…