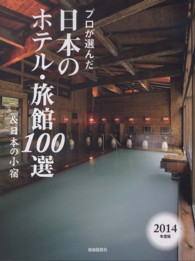出版社内容情報
学殖ゆたかな著者が,その円熟期に達して随処に得た広汎な学術的資料を蒐録した書であるとともに,人間として深い自覚に到達した際の,学者的真摯さを示した得難い手記である.その表現は要をえて簡潔,近世随筆の白眉たるは勿論,近年擡頭し来たった日本思想史研究に対して,種々の問題を提起する. (解説 家永三郎)
内容説明
「中臣寿詞」に始まり「道」に終る千一条の記述より宜長の根本思想をうかがうことができる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
15
巻末に目録と索引があります。そうそう、これ便利だから欲しかったんだよね。もちろん上巻もカバーしています。「神の道は、世にすぐれたるまことの道なり、みな人しらではかなはぬ皇國の道なるに、わづかに糸筋ばかり世にのこりて、たゞまことならぬ、他の國の道々のみはびこりにはびこれるは、いかなることにか、まがつひ神の御こゝろは、すべなき物なりけり」(227頁)2015/10/02
Ucchy
1
宣長のブログという感じ。西洋のことが「遥かなる西の国」として出てきたりする。今と違って頻繁に旅行に行けるわけでもなくインターネットもない江戸時代だけど、読書や人からの話、それらによって得た知識を元にした思索で江戸時代の人も驚くほどいろんなことを知っていたんだなと思う。巻末の解説が簡潔で分かりやすかった。2017/06/09