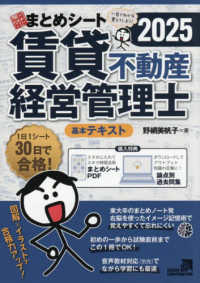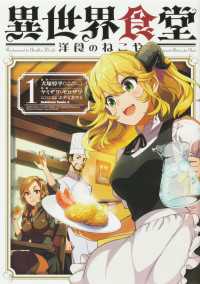出版社内容情報
花の錦の下紐は 解けてなかなかよしなや――。永正十五年(一五一八年)、一人の世捨人が往時の酒宴の席を偲んで編んだ小歌選集。春の妖艶たる雰囲気をまとって開巻が告げられ、多彩な表現をとった流行歌謡が、恋・枕・老い・面影・海辺などの群となって見事に配列されていく。中世末期の世相や習俗、人々の感性がうかがえる。現代語訳つき。
内容説明
花の錦の下紐は解けてなかなかよしなや―。永正15年(1518年)、一人の世捨人が往時の酒宴の席を偲んで編んだ小歌選集。春の妖艶たる雰囲気をまとって開巻が告げられ、多彩な表現をとった流行歌謡が、恋・枕・老い・面影・海辺などの群となって見事に配列されていく。中世末期の世相や風景、人々の感性がうかがえる。現代語訳つき。
目次
(真名序)
(仮名序)
本文
(奥書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さゆ
177
作者編者ともに不明で、世捨て人の僧たちが書いたとされるコンピレーションアルバム的な作品集。雨や風の音も自然の歌と捉えていたり、花の香りは誰にも分け隔てないこと、今日を明日の過去とするような時制を使ったテクニカルな作品もありおもしろい。Aqua Timezの絵はがきの春やBUMP OF CHICKENの宇宙飛行士への手紙なども似た表現あるなと思いつつ、もしかしたら今も昔も、表現手法が変わっているだけで感性部分に違いはあまりないのかもと感じた。2024/08/02
藤月はな(灯れ松明の火)
59
「順繰りに頁を捲って詠んでも良し。枕元に置いて気になった歌から目を通しても良し」な造りが嬉しい。小野小町伝説や謡曲のネタも盛り込まれているので知っている人はオタク心が鷲掴みになる事、間違いなし!結構、後朝後の幸福感や侘しさ、忍ぶも今にも綻びそうな恋心、恨みに思いつつも憎み切れない心情、相手の秋波をいなしつつも恋の遊戯を愉しむ姿などを詠う婀娜っぽい作品が多いです。2023/04/10
AN
15
時は室町時代。中世の戦国時代に、ある世捨て人が編んだ当時の小歌集の現代語訳と解説。帯にある「何せうぞ くすんで 一期は夢よ ただ狂え」という歌が印象的だか、この歌は逆に例外的かと思うくらい四季折々の風情のある恋の歌が多い。声に出して読む、または歌う事を想定されているのか、テンポがよいものが印象的だった。読み人知らずの歌が多く、決して洗練されているものばかりではないが、当時の人々の率直な気持ちや感性を楽しめる。恋の歌はストレートな気持ちを表現しているものが印象的。2023/06/25
青柳
4
時は室町後期、戦国時代。富士山を一望できる庵に暮らす隠者が集めた詠み人知らずの歌謡を、中国の「詩経」になぞらえ、これを「閑吟集」と命名し後世に伝えた歌謡集。本書に収められた三百十一首中、全体の三分のニが恋歌で占められ、どの作品も四季折々の自然や風情の中に、世の無常や郷愁、想い人への切々なる悲恋を歌い上げている。一つ一つの歌謡の中に、漠とした寂寥感が広がっており、現代を生きる読者は、名の知れぬ中世の人々の研ぎ澄まされた感性を通じて、歌い手が現実の彼方に視たであろう無常の世界の深淵を垣間見ることが出来る。