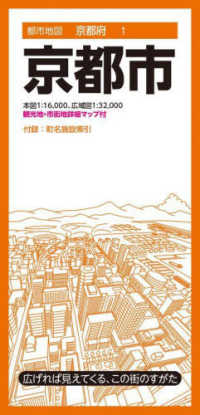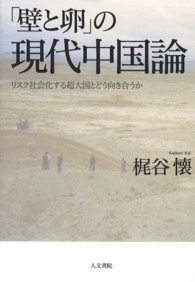出版社内容情報
全篇「今は昔」で始まり乾いた筆致で仏と人間の世界を描き尽くす,日本説話文学の最高峰.天竺(インド)・震旦(中国)・本朝(日本)の3部構成で,本文庫では「天竺・震旦部」1冊,「本朝部」3冊に約400話を抄録.
内容説明
全篇「今は昔」で始まり乾いた筆致で仏と人間の世界を描き尽くす、日本説話文学の最高峰。天竺(インド)・震旦(中国)・本朝(日本)の三部構成になっており、本文庫では「天竺・震旦部」一冊、「本朝部」三冊に約四〇〇話を抄録。
目次
聖徳太子、此朝にして、始めて仏法を弘めたる語 第一
行基菩薩、仏法を学びて、人を導ける語 第二
役の優婆塞、呪を誦持して、鬼神を駆へる語 第三
婆羅門僧正、行基に値はむが為に、天竺より朝に来れる語 第七
鑑真和尚、震旦より朝に戒律を渡せる語 第八
弘法大師、宋に渡りて、真言の教へを伝へて帰り来れる語 第九
伝教大師、宋に亘りて、天台宗を伝へて帰り来れる語 第十
慈覚大師、宋に亘りて、顕密の法を伝へて帰り来れる語 第十一
智証大師、宋に亘りて、顕蜜の法を伝へて帰り来れる語 第十二〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
60
本朝部上巻は、11~17巻の仏法説話の抜粋。聖徳太子の誕生・仏教布教を記した1話から、行基、鑑真、最澄、空海と高僧の説話、都周辺の寺院の縁起が続く。後半は、観音の功徳を得た話が多く、当時の観音信仰が広まりがよく分かる。肥後の書生が道に迷って羅刹に遭った話(12巻28)は真に迫るものがあり、観音に連れられ龍宮に行って金持になる話(16巻15)はわざわざ龍宮にまで行くという奇想天外さが面白かった。立山の地獄の説話もいくつかあり、修験者たちによって地獄谷や餓鬼の田がある弥陀ヶ原が地獄として語られていたようだ。2017/02/02
syaori
50
「今は昔」と語り始められる説話集。日本に仏法を根付かせた厩戸皇子の話から始まって、それを広めた空海・最澄や鑑真の話、寺や法会の縁起、僧などの往生譚、法華経や観音菩薩の功徳などが語られます。女性の脛を見て雲から落ちた久米仙人、安珍・清姫やわらしべ長者として流布していく物語のほか、覚えのあるお話もたくさん。仏法の伝来やお寺の縁起などはひと続きの絵巻物を見るような趣があってありがたい気持ちになりますが、菩薩の霊験譚など当時の生活や信仰が窺われるものが楽しかったので、エンジンがかかってきたところで次巻へ! 2018/01/15
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
6
購入は2001年、読了は2007年以前。平安時代末期に成立した、計千話を超える日本最大の説話集。その本朝(日本)部から、約四割を抄出したもの。上巻は十一巻から十七巻までで全て仏法部になっている。聖徳太子が日本で始めて仏法を広めた話から始まり、日本史における上人伝、仏様の利益によって救われた様々な霊験譚へと続く。現代語訳はないものの脚注は充実しているし、古文の中ではかなり読みやすい方なので、日本の古典愛読者には原文で読んで欲しい。簡潔ながら臨場感のある名文を感じられるはず。日本のショート・ショートの古典だ。
青島
2
法華経、観音、地蔵すごすぎる。2010/09/28
ホレイシア
2
「今は昔、比叡の山の…」というのを暗記させられたのがきっかけだったが、古語の美しさに気づかされた本。
-
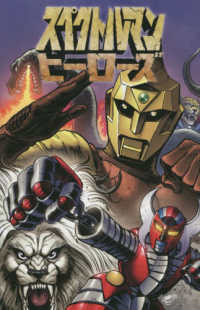
- 和書
- スペクトルマンヒーローズ