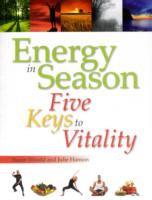出版社内容情報
紀貫之ら四人に勅撰和歌集作成の命が下ったのは延喜五(九○五)年のことであった.『万葉集』以後長いあいだ,公の席では漢詩文が隆盛を極めていただけに,選者たちの喜びは大きかったに違いない.約十年の歳月をかけ,古今の和歌を精選して成った.作風は万葉風にくらべ理知的・内省的で技巧に富み後世に絶大な影響を与えた.
内容説明
紀貫之ら4人に勅撰和歌集作成の命が下ったのは905(延喜5)年のことであった。『万葉集』以後、公けの席での漢詩文隆盛の中で、はじめて「やまとうた」を選ぶ貫之たちの喜びは大きかったに違いない。10年の歳月をかけ古今の和歌を精選して成った。作風は万葉風にくらべ理知的・内省的で技巧に富み、後世に絶大な影響を与えた。
目次
春歌
夏歌
秋歌
冬歌
賀歌
離別歌
羇旅歌
物名
恋歌
哀傷歌
雑歌
雑体
大歌所御歌・神遊びのうた・東歌・墨滅歌
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
389
醍醐天皇の命により紀貫之等が編纂し、延喜5(905)年に奏上。世に名高い最初の勅撰和歌集。部立・構成また歌そのものも、長らくその後の勅撰集の規範となった。貫之の手腕なのか、編集方針は実に整然としている。それ以前に準拠するものがないだけに、選歌にも編纂にもそうとうに苦労したことだろう。歌人別では貫之の102首を筆頭に凡河内躬恒 60首、紀友則 46首と続くが、恋の部となると業平が断然精彩を放ってくる(次いでは小町か)。これ1首は選びにくいが、ついつい『伊勢物語』に魅かれて「月やあらぬ…」に手を挙げてしまう。2021/03/25
新地学@児童書病発動中
107
この歌集を少しずつ読んでいくのは、本当に楽しかった。日本語の言葉の響きや陰影を味わいながら、じっくり読んだ。一つ一つの言葉にこめられた先人たちの喜びや哀しみが、どの歌からも鮮やかに伝わってくる。正岡子規や萩原朔太郎はこの歌集を貶している。特に萩原朔太郎は「読むに堪えない」と強い批判だ。残念な批判だが、この二人の気持ちは分かるような気がする。古今和歌集の歌には、一人の人間がこの世界に向かい合っているという個の感覚が少ない。近代的な自我を持とうとした明治の以降の文学者が(続きます)2018/02/16
しゅてふぁん
31
平安貴族の必須教養、古今和歌集を読んでみる。1111首を読み切るのはなかなか骨が折れました(^^; とはいえ、今日はここまでと本を閉じても、やっぱりもうちょっと、とまたすぐに読みたくなる。そんな魅力を持った和歌集だった。読み返すというよりは、気まぐれに開いたところを読んでみるとか、季節や気分に合った歌を読んでいくことになりそう。この和歌集の全ての歌を暗記していたという村上帝の女御様は凄いわ。せっかくなので古今集についての解説書を色々と読んでみようかな。2018/02/17
デビっちん
26
再読。パッと感じたままに開いたところを読んでみると、見事に心に響く歌があることが多いです。で、そのまま少し読み続けてしまいたくなる不思議な魅力があります。季節の変わり目にあわせて読むのも趣があってよさそうです。高校生のとき古文好きだったんですよねー。2018/08/09
双海(ふたみ)
25
前回読んだときに気に入った歌をチェックしてありました。今回もまたチェック。新たに気に入った歌もありました。どんどん書き込んでいます。「山ざくら霞のまより ほのかにも見てし人こそ恋しかりけれ」・「春たてばきゆる氷の のこりなく 君が心はわれにとけなむ」・・・2首目なんかは明治時代の明星派の中にポンと入れても違和感がなさそうな気がします。2016/06/03
-
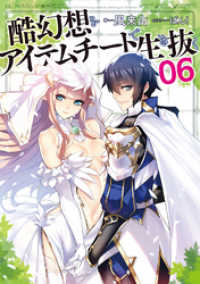
- 電子書籍
- 酷幻想をアイテムチートで生き抜く 6 …