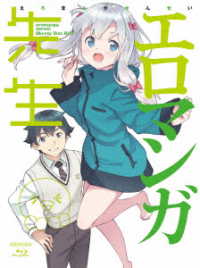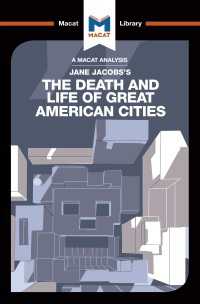内容説明
学問が、純粋な好奇心や社会問題の解決、人々の幸福のためでなく、国家の進める軍事戦略や兵器開発に従属させられるような社会を、再び到来させてはいけない。そのような社会は民主主義にとっての危機であるとともに、学問の危機でもある。科学研究のパラダイム設定自体に軍事が深くかかわり、学問世界は浸蝕され、研究者の頽廃が進む。
目次
第1章 科学者のあり方
第2章 戦後、科学者は軍事研究とどう向き合ってきたか
第3章 防衛省の戦略
第4章 大学改革にまとわりつく軍学共同
第5章 米・「軍産複合体」と科学者
第6章 独・軍学共同反対の運動
第7章 「軍民両用技術」という甘い罠
第8章 キャンパスから声をあげていく
著者等紹介
池内了[イケウチサトル]
名古屋大学名誉教授。宇宙物理学、科学・技術・社会論
小寺隆幸[コデラタカユキ]
京都橘大学人間発達学部教授。数学教育学。公益財団法人原爆の図丸木美術館理事長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
39
この間の市民大学院のA研究員からご教示いただいた、大学と軍需産業の関わりのテーマだったので、借りてみた。小寺教授によると、学問が、純粋な好奇心や社会問題の解決、人々の幸福のためでなく、国家の軍事戦略や兵器開発に従属させられるような社会を、再来させてはいけないという(6頁)。御意。池内名誉教授によると、軍事研究に勤しむことは、研究の目的が人々の幸福のための真理追究でなくなることを意味するから、2017/03/09
更紗蝦
12
科学者や大学が軍産複合体に取り込まれることの危険性について論じた本です。2015年度から始まった「安全保障技術研究推進制度」によって日本では大学での軍事研究が公然と開始されてしまっており、「政治的なもの」を毛嫌いする割には学問の場が政治的に利用されること関しては鈍感な日本人のダブスタぶりには寒気を感じてしまいました。探査機「はやぶさ」はさんざん話題にしておきながら、2012年にJAXA法が改定されてJAXAが軍事研究を行うことが法的に可能になったことは全く話題にならなかったことも、思い返すとゾッとします。2017/05/01
おおかみ
6
じわじわと進む「軍学共同」に警鐘を鳴らす。象牙の塔とは言うものの、学術は社会を大きく変容させるものであり、当然安全保障にも関わりうる。「デュアルユース」の反論は理解できるし、研究費が逼迫する中科学者には大局的な視野と崇高な倫理観が求められるのだからそれは同情するところだが、やはり揺るぎない信念はあってほしい。2016/11/01
アカショウビン
3
池内先生の名前が気になり図書館で借りたが、2016年の本だった。ウクライナの戦争もガザの状況も、本書の心配する方向へ大学を導く風になっているのかと不安になる。菅政権の時に「日本学術会議」なるものに注目が集まったが、本書を読む限り、実に志の高い団体なのだと理解した。「安全保障技術研究推進制度」の導入は、全くよく練られた「研究者版の経済的徴兵制」であり、豊橋技術科学大など、いかにもからめとられたという所から東工大、北大の名もある。しかし今にもミサイルが飛んで来そうな昨今、ゆっくり議論の時間はあるのか。2025/06/12
call
2
学問は軍事研究とどう向き合うべきかというテーマの本。この本の結論は学問にとって軍事研究は絶対に避けるべきものだということ。科学が軍事利用されてきた歴史的事実に触れながら科学者たちの倫理を問うている。また、安倍政権が学問を軍事研究へと誘導しようとしている点にも触れられている。最後にキャンパス内での取り組みを述べている。学問の自由は確かに重要だが、軍事研究をする自由もあると思う。本書でも述べられていたが学問の自由よりも研究者が自分の研究に責任を持てなくなることの方が深刻に思えた2017/03/14