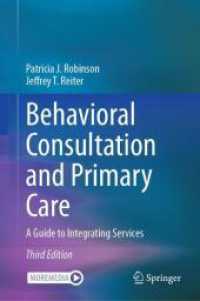内容説明
「ゆとり教育」から「確かな学力」路線への転換以降、学力格差は縮小されたのか。男女差や通塾・家庭環境による違いはどうか。格差を克服する学校の特徴とは。「学力のふたコブらくだ」(二極化)状況を解き明かし大きな反響をよんだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』(2002年)の後継調査から、最新の状況を検証する。
目次
1 学力格差の時代
2 学力のトレンド
3 学力の男女格差
4 家庭環境と学力格差
5 「格差」を克服する効果のある学校
著者等紹介
志水宏吉[シミズコウキチ]
1959年兵庫県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科教授。学校臨床学、教育社会学
伊佐夏実[イサナツミ]
1979年京都府生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科助教。教育社会学
知念渉[チネンアユム]
1985年沖縄県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科助教。教育社会学
芝野淳一[シバノジュンイチ]
1986年兵庫県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程。教育社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
22
非正規では未婚。未婚ゆえにフランスとは違い、婚外子は生まれても日本では疎外される。保護者の世帯収入300万円未満(7頁表Ⅰ-2)とは、両親もしくは母子家庭であれば、1人当たりの取り分が150万円。こんな低所得では、学習支援業にお金は出せれない。学力格差をいうのなら、ODでも結婚ができ、非正規でも結婚できる条件を整えるべきである。しかも、10年早ければ日本の人口ピラミッドや極点社会もあれほど極端な少子高齢人口減少にはならなかったのかと思うと、 格差は悪くない、という当時の小泉首相の発言も間違っていた 2014/06/22
カラス
4
社会関係資本(人と人とのつながり)が成績にたいしてそこそこ関係があるという調査結果はとても興味深い。確かにこれは「格差を乗り越える一筋の光」P48、だろう。それ以外にも、女子の自己肯定感の低さや、「ゆとり」時代においても下がらない小学女子の国語の成績も印象に残った。タイトルに調査報告とあるとおり、基本的には報告書で、淡々とした内容なのだが結構面白かった。今後は、こういう本も読んでみようと思う。前著にあたる『「学力低下」の実態』も良さそう。2019/09/27
新橋九段
2
経済資本と文化資本が学力に影響を与えるという一般に言われている仮説を確認。つながりもある程度関係すると。2014/07/02
nekora
1
アンケート項目や対象から漂う物凄い「街灯の下で鍵を探す」感。民間企業の品質管理でこんな調査と結論やったら許されんな…。2017/07/20
おだまん
1
案外意外な結果かも。2014/07/14