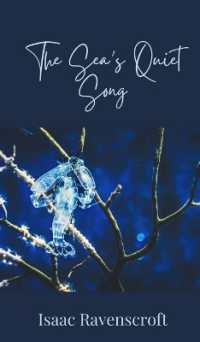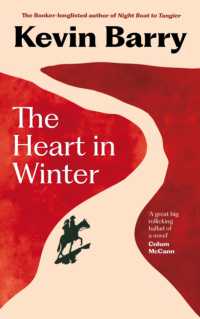出版社内容情報
二〇世紀ロシアの思想家ミハイル・バフチンによる〈対話〉の思想が、近年、教育や精神医療の現場で注目されている。単なる話し合いではない、人を決めつけない、つねに未完成の関係性にひらかれた対話とは何か。「複数の対等な意識」「心に染み入る言葉」など、バフチン自身のテクストを紹介しながら、ポイントをわかりやすく解説する。
内容説明
二〇世紀ロシアの思想家ミハイル・バフチンによる“対話”の思想が、近年、教育や精神医療、文化交流などの現場でひろく注目されている。単なる話し合いではない、人を決めつけない、つねに未完成の関係性にひらかれた対話とはなにか。バフチン自身のテクストを実際に紹介しながら、「心に染み入る言葉」「複数の対等な意識」「内的対話」「創造的理解」「異言語混淆」など、バフチン対話論のポイントをわかりやすく解説する。
目次
1 対話的人間(「わたしはひとりで生きている」という幻想;ひとは永遠に未完であり、決定づけられない;ポリフォニー―自立した人格どうしの対等な対話 ほか)
2 内なる対話(モノローグが対話的なこともある;意識は対話の過程で生まれる;真理も対話のなかから生まれる ほか)
3 相互作用のなかのことば(言外の意味;言語のなかでは、さまざまなことばが対話をしている)
著者等紹介
桑野隆[クワノタカシ]
1947年生まれ。東京外国語大学大学院(スラヴ系言語)修了。元早稲田大学教授。専攻はロシア文化・思想(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
Kerberos
hidehi
阿部
たろっくす
-

- 洋書
- Impressions