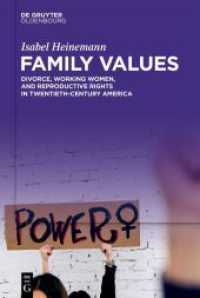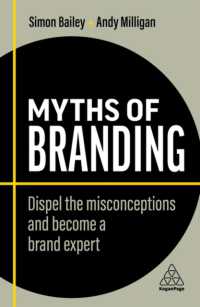出版社内容情報
簡単に一つのことだけ書く文章とはどういうものだったか.――急逝した著者が遺した最後のことばたち.
目次
1 大きな字で書くこと(斎藤くん;大きな字で書くと;井波律子さんと桑原『論語』;森本さん;日本という国はオソロシイ ほか)
2 水たまりの大きさで(イギリスの村上春樹;「あらーっ」という覚醒;知らない人の言葉;フラジャイルな社会の可能性;大きすぎる本への挨拶 ほか)
著者等紹介
加藤典洋[カトウノリヒロ]
1948‐2019年。文芸評論家、早稲田大学名誉教授。著書に、『言語表現法講義』(岩波書店、1996年、第10回新潮学芸賞)、『敗戦後論』(1997年、ちくま学芸文庫、第9回伊藤整文学賞)、『小説の未来』『テクストから遠く離れて』(2004年、朝日新聞社/講談社、両著で第7回桑原武夫学芸賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
51
遺言のような、この本を読み終えた今、とても悲しい。加藤さんの来し方やお父さんとの確執、影響を受けた人々のエピソード、日本や世界の行く末を案ずる思い・・・。自分の中に二つの場所を持つこと、二人の感情を持つこと、その大切さを痛感していると最後の章(2019年3月2日 信濃毎日新聞)にある。これが響いた。昔、加藤さんはB6の400字詰め原稿用紙に小さな字で文章を書いていたそうだ。今、簡単に一つのことだけ書く文章、それを思い出そうとして、大きな字で書いてみるのだと・・・深い言葉だ。2020/08/28
trazom
47
昨年5月に亡くなられた加藤典洋さんの遺稿。「敗戦後論」で、左右両派から強い批判に晒された加藤さんだったが、ぶれないこの人の信念の源を垣間見ることができる文章の数々である。特高警察に加担していた父の戦後の態度への徹底的な批判、憲法9条の平和主義に基づかない非武装中立論としての森嶋通夫先生の評価、思想的には対極であるはずの久保卓也氏の国防論への評価など、加藤さんのフェアな態度は変わらない。ご入院前から書き始められた原稿だが、自分と関わった人たちとの記憶を紡ぐ文章には、寂寥感が溢れていて、胸が締め付けられる。2020/02/04
おさむ
38
昨年、逝去された文芸評論家の加藤典洋さんのエッセイ集。父親の仕事の関係で転校を繰り返した幼いころ、山形から上京して出会った忘れられぬ人々、そして話題を集めた1995年の「敗戦後論」を巡るあれこれ。独特の語り口が印象的でした。とくに、サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」に端を発する論考は面白い。catch(手で守る)からwatch(見守る)への転換とは、教えることの双方向性、つまり、教える側も学ぶ(人を信頼する)という事を見事に物語っている。2020/02/10
ころこ
36
編集や筆入れが無い状況から、絶筆かと想像します。内容の割に高価で、相当の興味が無いと落胆します。中学生の頃、自らの不注意で交通事故に遭う話があります。そこでは、無事であった息子を警官という職務から叱責する父親との齟齬が書かれています。他方で、大人になって、実は特高の任務を受けていたことが判明し、問い詰める話がこの父親との仲良くないエピソードとしてあります。屈折を抱えたまま、時間を掛けて別の何かを生み出していく。B6の原稿用紙に小さな字で仕事をしていた著者が、大きな字で書くとしたら父親のことでしょうか。2019/11/20
かふ
23
部屋の掃除をしていて、いつだったか買った本を読み始めたら止まらなくなってしまった。加藤典洋が亡くなった後に出たエッセイ。学生時代は小さな字で論文のようなものを書いていて、そしてパソコンでも小さな字で書いていたが、手書きの大きな字で書くということ。ゆっくり考えながら書くということなのか。特高警察であった父についての文章、加藤典洋の代表的評論『敗戦後論』で描けなかった自身についての「敗戦後論」を書いている。一般論ではなく、個人としての感情と父親との対峙。その言葉は、ある面父への追悼の言葉だったのかもしれぬ。2021/05/31