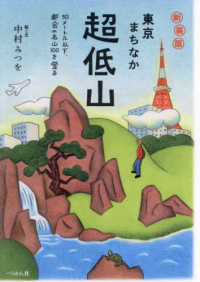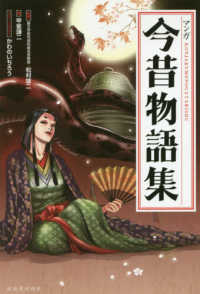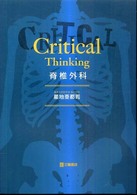内容説明
新しい学習指導要領の登場、教育委員会制度の改革、保護者・地域の学校参加制度、教員の資質・能力向上政策…。それで結局どうなったのか、どうなるのか?「改革疲れ」が指摘される現場にむけて、理想と現実のギャップと「副作用」、「立ちどまって問い直すための視点」を提示。教育分野を牽引する、頼りになる研究者による、四年ぶりの単著。
目次
1 中央の教育改革(近年の教育改革(論)をどうみるか―ましな改革を選んでいくために
日本の公教育はダメになっているのか―学力の視点からとらえ直す
対談・新しい学習指導要領は子どもの学びに何を与えるか―政策と現場との距離
なぜいま教育勅語?
「昔の家族は良かった」なんて大ウソ!自民党保守の無知と妄想―家族教育支援法案の問題点
教育改革のやめ方―NPMをめぐって)
2 教育行政と学校(地方の教育行政に期待するもの―新しい時代の学校教育;学校教育のいまと未来;地方分権と教育;「学校のガバナンス」の光と影;保護者・地域の支援・参加をどう考えるか)
3 教員の養成と研修(教員の資質・能力向上政策の貧困;教員集団の同僚性と協働性;「教員は現場で育つ」のだけれど;教育の複雑さ・微妙さを伝えたい)
著者等紹介
広田照幸[ヒロタテルユキ]
1959年生まれ。日本大学文理学部教授。専攻は教育社会学。日本教育学会会長(2015年8月~)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
21
教育改革と教育行政全般の話でタイトルの「やめ方」は本書の一部。様々な著者の投稿を集めたものなので、章ごとに統一感はなく内容も所々重複している。日本の公立学校は他の先進国と比べ低予算ながらよい教育をしている。これ以上望むのは教員数(予算)を増やすしかないが財務省はさらに減らす方向。教育学は特に教師にとってとても役に立つが軽視されている。自分本位のトンデモ教育を語る多くの政治家の先生たちにもっと教育学を学んでほしいが無理だろうなと著者は嘆いて締めくくっている。教育学、特に教育哲学の大事さが改めて分かる。2020/01/22
Ryosuke Kojika
9
また1人、他の本も読みたい著者に出会った。これまでに様々な研修を受けたが、どの研修よりも有意義であるし、教育に携わるどの層も読むべきものだと思う。学びが多すぎる。無限に増え続ける需要に応えるには、まずその需要が真っ当であるか、応じるに値するものかを見極める。そして、その実現に必要な供給量に着目する。量を増やすか、生産性を高めるか。需要だけ増大し、供給側に目を向けていなさすぎる。現場の疲弊は必然だし、疲弊した現場から質の高い教育が行われる訳がない。教育は誰でもが語れるからこそ、教育学のバックボーンが重要か。2022/12/01
見もの・読みもの日記
7
「日本の学校はよくやっている」という評価を前提に、子どもたちに主体的に考えさせ、個性を重視した教育を実現するには、教員の試行錯誤や「深い学び」が許容される、ゆとりある環境が必要と説く。予算措置を伴わない性急な改革、評価や競争による締め付け、「現場の知」の過度な重視への批判などに共感した。大学改革のやめ方にも通ずると思う。2019/11/14
May
3
脱ゆとりに舵を切った学習指導要領後となる09~17年の著作と講演の集成で、安倍政権下で進められている教育改革に異議ありとする内容がメイン。十分な人的資源等を与えるべきとする主張など正論と感じるものが多い。一方で、教育再生会議などで出てくる意見にもそれなりの理由があるはず(現場経験者や教育学研究者がほとんどいない会議だとしても)と私自身は考えるのだけれど、そういった姿勢が見えないところは残念。2024/05/03
おサゲっち
3
前半はデータに基づき、日本の教育は悲観するに当たらないことを述べ、後半に(たとえば14章「教員は現場で育つ」のだけれど、、、)を通じ、今後の日本教育のビジョンを示している。現場成長主義に留まらない、教職大学院や外部研修を強く勧めている。そして若い教員だけでなく、ベテラン教員にも新たな事態の突入に対応できるよう、学び、探し、学校に持ち込んでほしいと綴っている。そのために教員増、外部協力を強く主張もしている。読み進めるほどに主張が納得できた。2020/06/17
-

- 電子書籍
- 嫌われ夫婦の幸福家族計画【タテヨミ】第…
-
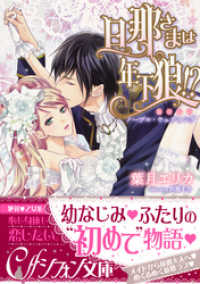
- 電子書籍
- 旦那さまは年下狼!? 恥じらいノーブル…