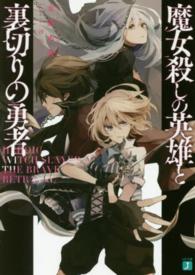内容説明
中世末期以降、国家とは内実や権力の担い手を問わず、ひとつの法秩序のみを存立の根拠とするようになった。そして、この法秩序を支える言説の核心、つまり国家と法を成立させる要諦となったのが、“主権”という概念である。近代ヨーロッパが重ねてきた議論の歴史、日本における二つの憲法制定過程、そしてその間にあった国体をめぐる論争…膨大な資料を読み解きながら、主権論という未踏の領域へ挑む。俊英による新たなる思想史。
目次
序章 主権と主権者(法と法外なもの;主権国家の死? ほか)
第1章 法秩序の近代(主権の概念;主権者とは「誰」か ほか)
第2章 近代法秩序の“創造”―明治憲法体制の場合(主権概念の受容;統治権―井上毅の挑戦 ほか)
第3章 近代法秩序の瓦解と“再創造”(「国体」の賦活;国体論の傍らで ほか)
著者等紹介
嘉戸一将[カドカズマサ]
1970年大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程中退。相愛大学准教授を経て、龍谷大学准教授。専攻は法思想史、政治思想史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Masatoshi Oyu
2
これも難しい。内容を理解するには西洋の哲学やらの知識も必要。でも明治日本の主権概念の受容のところなど興味深いところも多いので、これをきっかけに勉強してまた戻ってきたい。2022/05/02
白いハエ
1
欧米諸国の主権論のアウトラインを追った後、明治維新における主権論の受容とその議論を緻密に論じる大書。明治日本の主権論の受容の困難、天皇に活路を見出ししたことは確かに創造的であるとも言えるが、現状としても、主権者論=決断主義を回避する、準拠を巡る問題はあり続けており、考え続ける意味はあるのだろう。2020/06/30
ただの人間
0
主権(正統性)と主権者(決断者)を慎重に区別し、特に維新期から第二次大戦後の日本国憲法制定期までの日本における議論とそれに関連する外国の議論を中心に論じる。副題にあるローマ法に関しては、(そもそもローマに主権概念自体が存在しなかったこともあり)法諺とそれに関連する中世以降の議論を追うという形で触れられていた。主権(者)に関して文字通り古今東西様々な議論がなされてきたことが伺え、その中で「無」の観念も参照しつつ主権論に決断主義に陥らない正統性という固有の意味を見いだそうとする結論部の問題意識は印象的だった2020/05/31
-
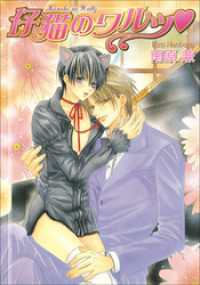
- 電子書籍
- パレット文庫 ショパンシリーズ2 仔猫…
-
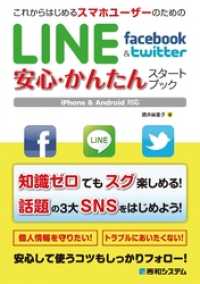
- 電子書籍
- これからはじめるスマホユーザーのための…