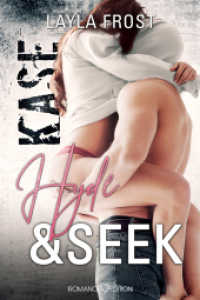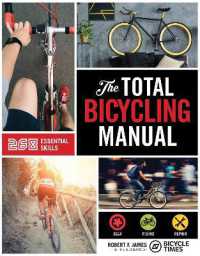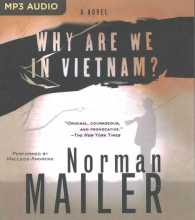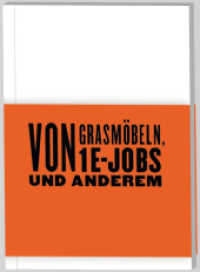出版社内容情報
対話型サービスChatGPTは驚きをもって迎えられ、IT企業間で類似サービスをめぐる激しい開発競争が起こりつつある。それらを支える大規模言語モデルとはどのような仕組みなのか。何が可能となり、どんな影響が考えられるのか。人の言語獲得の謎も解き明かすのか。新たな知能の正負両面をみつめ、今後の付き合い方を考える。
目次
序章 チャットGPTがもたらした衝撃
1 大規模言語モデルはどんなことを可能にするだろうか
2 巨大なリスクと課題
3 機械はなぜ人のように話せないのか
4 シャノンの情報理論から大規模言語モデル登場前夜まで
5 大規模言語モデルの登場
6 大規模言語モデルはどのように動いているのか
終章 人は人以外の知能とどのように付き合うのか
著者等紹介
岡野原大輔[オカノハラダイスケ]
1982年生まれ。2010年東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了、博士(情報理工学)。2006年Preferred Infrastructureを共同で創業、2014年Preferred Networks(PFN)を共同で設立。現在、PFN代表取締役最高研究責任者およびPreferred Computational Chemistry代表取締役社長を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
-





Hr本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
115
ChatGPTの出てきた背景やその理論的な構成を説明してくれています。結構早い時期に書かれたもので最近の状況などはあまり書かれていないのですがとっかかりとして読むのにはいいのかもしれません。ただ小冊子の割には内容はかなり高度であるという気がします。わたしはChatGPTを利用する観点での本はいくつか読みましたがやはり基本的な論点からはこの本はいい本だという気がします。2024/08/05
チャーリブ
40
急速に私たちの生活に入り込んできたチャットGPTを支える大規模言語モデル(LLM)についての概説書。チャットGPTで分かるように、LLMはとても優秀ですが、ありもしない情報を捏造する(「幻覚」と呼ばれています)という困った一面があります。また将来的に人間に対して有害な存在とならないかという懸念もあります。文の意味や構造も理解し、文を生成することもできるレベルになっているLLMは、限りなく知能に近づいているのは確か。LLMは遠からず私たちの生活の一部となるでしょうが、大丈夫でしょうか?○2023/10/24
33 kouch
33
人工知能はあくまで単語の予測の繰返しであり、理解ではない。となると、やはり人間とAIには理解や認知というところでは差がある。、と思ったが、では理解や認知って改めてなんだろう?とも思ってしまう。禅問答みたいに。いずれせよAIは人間から何か奪うものでなく、人間がより便利になるためにあるツール。チェスで人間に勝った人工知能の話が印象的。それによりチェスの技術はより磨かれ、人々はこの競技に注目するようにもなった。人間は勝つことでなく、強さを追求するその戦いに憧れている。人工知能は間違いなくチェス文化を前進させた。2024/02/09
塩崎ツトム
27
「本文中学習」だの「自己注意機構」だのの説明を読むと、人工知能のやっていることはかーなり人間の頭ん中と近いという印象を受ける。2023/11/07
テイネハイランド
25
邦訳本「ChatGPTの頭の中」の読メレビューで入門書としては本書のほうがわかりやすいとあったので読みました。別に岡野原さんの本「ディープラーニングを支える技術 」も持っているのですが、本書は更に一般向きに大規模言語モデルを用いたAI(chatGPTなど)について解説した本です。日本を代表するベンチャー企業の幹部による本だけあって対象レベルに合わせたプレゼンの仕方がうまく、読者にわかった気にさせる能力はとても高いと感じられますが、ディープラーニングの仕組みなどについては別の本で補う必要があると思います。2024/01/20