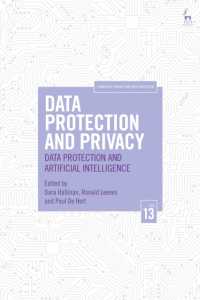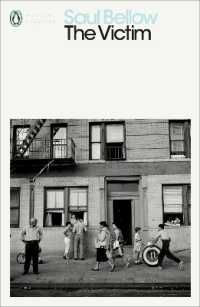出版社内容情報
驚異的に発展し社会に浸透する科学の影響はいまや誰にも正確にはわからない。科学技術に関する意思決定と科学者の社会的責任の新しいあり方を、過去の事例をふまえるとともにEUの昨今の取り組みを参考にして考える。
内容説明
驚異的な発展をとげ深く社会に浸透する科学。その営みは絶えず未解明の部分を含んでおり、科学が社会に及ぼす影響は誰も正確にはわからない。この状況で科学者は、誰に対していかなる責任を負い、それをどのような形で果たせばよいか。日本における過去の責任論や事例を検討し、EUの新たな取組み(RRI)を参考に、「責任ある研究」のあり方と、それを可能にする社会のデザインを考える。
目次
1 社会的存在としての科学者
2 責任の三つの相
3 科学の原罪論と役割責任―日本における科学者の社会的責任論
4 不確実性下の責任
5 科学の倫理的・法的・社会的側面
6 責任ある研究とイノベーション
7 これからの時代の責任
著者等紹介
藤垣裕子[フジガキユウコ]
1985年東京大学教養学部基礎科学科第二卒業。1990年東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課程修了。学術博士。東京大学助手、科学技術庁科学技術政策研究所、東京大学大学院総合文化研究科准教授をへて、現在同教授。科学技術社会論・科学計量学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
52
科学者の発する言葉が、社会を動かすことが増えてきたのかと思う。それに頼ろうとする風潮の変化があるからだとも思う。但し、そこでの姿勢が大切であるとともに、大きな課題があるのが、今のこの国の状況かもしれない。科学は絶えず変化していくものである。このことを頭に置いておけるか否かが大切。最後のほうに述べられているリベラルアーツとシティズンシップ。ここに立脚すること。2025/05/15
takao
3
ふむ2021/08/17
ディス
2
◯。短い本だが注釈とかも細かく読んでいかないと難しい印象。とはい論点は興味深くて、著者の言うところのシティズンシップを持たねばならないということ、科学は常に進行していて、専門家の間でも意見が割れるのが基本であること⋯辺りは、見逃しがちだがそれはそうよねという感覚。災害時の避難するしないの微妙なラインの時にどうするか⋯みたいな話を考えた。最後は私が判断せねばならないし、揺れがあるのは仕方ない。2025/04/30
Go Extreme
2
三つの相分類 内部規律たる責任ある研究実施 研究不正超えた組織機関責任 科学技術の社会的製造物責任 市民の問いに応答する責任 固い科学観と現実科学のギャップ 不確実性下の先制的予防原則 朝永振一郎の科学の原罪論 ELSIによる倫理・法・社会側面考察 責任ある研究イノベーション 市民社会アクター協働のRRIプロセス 日本責任論と欧州RRIの対比 公共空間支えるリベラルアーツ教育 あたりまえ疑うラッセル教育論 制度設計力・視点転換力育む教育 専門家丸投げ排すシティズンシップ 状況解明と選択肢提示のSTS役割2025/04/29
brzbb
2
科学技術と社会の関係について、原発事故もパンデミックもそうだけどなによりAI技術をどのように受け入れるのか(あるいは受け入れないのか)がまさに現在進行形の問題としてある。研究不正をしないなどの研究倫理とは別に、科学者が社会に対してどういうかたちで責任を果たすかというのは、社会のありかたや市民の成熟度によっても変わってくるというのはなるほどと思った。専門家と素人である市民が直接専門的な議論するのは不可能だけど、社会におけるステークホルダーとして市民の参加は絶対に必要なわけで。2024/04/12
-

- 電子書籍
- ようこそ仙界! 飛べない舞姫と月影の告…