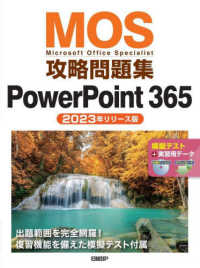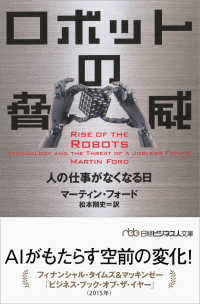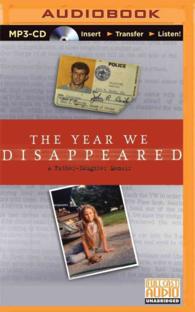出版社内容情報
アフリカの大地で巨大蚊柱と格闘し、かたや研究室で万単位の蚊を飼育する著者が語る蚊の奇妙な生態。
内容説明
オスと交配したメス蚊だけがまさに人を襲うバンパイアと化し、ときに恐るべき病原体を人の体内に注入。吸血された人を“患者”というものに変えてしまう。アフリカの大地で巨大蚊柱と格闘し、アマゾンでは牛に群がる蚊を追う。かたや研究室で万単位の蚊を飼育。そんな著者だからこそ語れる蚊の知られざる奇妙な生態の数々。
目次
1 その蚊、危険につき
2 蚊なりのイキカタ
3 標的を発見!
4 蚊が血を吸うわけ
5 病気の運び屋として
6 蚊との戦いか、共存か
著者等紹介
嘉糠洋陸[カヌカヒロタカ]
1973年山梨県に生まれる。1997年東京大学農学部獣医学科卒業。2001年大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)。理化学研究所、米国スタンフォード大学などを経て、2005年帯広畜産大学原虫病研究センター教授。2011年から東京慈恵会医科大学熱帯医学講座教授。2014年から同大学衛生動物学研究センター長を兼任。専門は、衛生動物学、寄生虫学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
87
蚊のシーズンは去ろうとしているがこれは面白い。蚊を研究している著者の苗字(かぬか)にもう、かという文字がふたつも入っている。^^蚊が媒介する感染症デング熱やマラリアは世界中で見るといまだに感染者が多いようだ。。蚊の習性や生態について。なかでも「蚊が血を吸うわけ」という章ではどのようにして血を吸うのか、痒みの正体が興味深く読むことができた。血液型で刺される事が多いのか、吸血の仕組みなど全体を通して生物学や科学書にありがちな専門用語と独特な文章はなく平易でわかりやすく書かれている。2016/10/01
calaf
17
蚊の生態、そして蚊の媒体する病原体による病気、それらを研究する著者の研究紹介。非常に重要な研究とは思う。そしてこういう人がいるから、だんだんと世の中住みやすくなってきているのだとは思う。でも...個人的にはあまり近寄りたくない...という感じ (^^;;;2017/09/07
DEE
11
蚊を愛する著者が、蚊についてとても分かりやすく解説してくれている。 二酸化炭素、匂い、温度が蚊が認識するポイントらしい。 また蚊に刺されすぎるとIgG抗体ができ痒みを感じなくなる。もちろん痒みは人体への信号でもあるのでなければいいというものではないが、興味深い話である。2019/11/20
大先生
10
著者の蚊に対する愛情が凄い!「私は、蚊が血を吸うことは(とがめられることを承知で申し上げますが)大変美しい行為だと思っています。」と書かれています(笑)蚊が反応するのは①二酸化炭素、②匂い、③熱。O型が刺されやすいという説がありますが、まだ結論は出ていないそうです。人類が寒い地域に住むようになったのは蚊(が媒介する病気)を避ける意味もあったとか。蚊は寒さに強いが活動はしないから。蚊に刺されて痒くなるのはアレルギー反応。たくさん刺されると耐性ができる。でも、しばらく蚊に刺されないでいるとまた痒くなる。2025/02/15
conegi
8
蚊についての本。血を吸うメカニズムが解説されているが、やはり凄い。余りに合理的な構造は、生物というより機械なのではないかと考えてしまう。昆虫の宇宙飛来説も信じてしまいそうになりそう。蚊というと伝染病の媒介だが、蚊帳が地味ながらも効果的。しかし無償配布しても、投網に使われるというのは少し笑ってしまう。いや、笑い事ではないのだけど。伝染を防ぐには、正しい知識を啓蒙する事は大事。終止著者の蚊への愛に溢れる本だった。2025/04/14