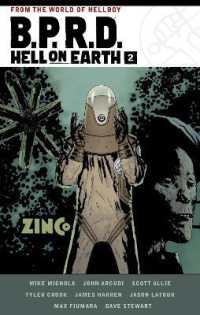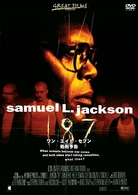内容説明
イロニーを身をもって生き、否定性を突きつめることで十九世紀市民社会の哲学や宗教理解を破壊し、実存、反復、不安などの鍵概念をもって現代哲学への扉を開いたキルケゴール。しかしながら、数々の仮名で扮装し、ときに自己の著作を否認しさえもする、この奇妙な男の理解は、一筋縄ではいかない。決定版伝記など近年の研究の進展を踏まえ、従来のイメージや解釈を批判しつつ、この独自のキリスト教的哲学者の核心に迫る。
目次
第1章 仮名、間接伝達、人と言葉の一致
第2章 人と生
第3章 ソクラテス、イロニー、否定弁証法
第4章 ¨asthetischなものの多義性
第5章 新たな経験としての反復、という逆説
第6章 「倫理」概念の変容
第7章 実存、実存すること、実存的(Existenz,existieren,existentiell)
第8章 美的宗教性に打ち込まれる楔としての実存倫理
第9章 晩年のアンガージュマン
著者等紹介
藤野寛[フジノヒロシ]
1956年生。1986年京都大学大学院文学研究科博士課程学修退学。1993年フランクフルト大学学位取得。現在、一橋大学大学院教授。哲学・倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
16
マジにならないで深刻ぶったものを軽々と小馬鹿にし皮肉るイロニーの使い手としてのソクラテスを、キリストに次いで師と仰いだ哲学者の解説。完全に体系化された理論からはこぼれてしまう個々の人間(実存)のあり方に焦点を当てて哲学した人物にふさわしく、不真面目なイロニーの精神を奉じてたのに恋愛ではマジになりかけた自らに気づいて愕然とし、大急ぎで婚約を解消した矛盾含みの人生も、かえって様になる。倫理と宗教よりも美的なものを強調する解釈はたしかに斬新。けれどもキリスト教まで笑い飛ばすことは、キルケゴールにはできなかった。2016/05/12
さえきかずひこ
13
キルケゴール理解において重要な反復概念などについて考察した第5章、また実存(Existentz)というドイツ語の語義の変遷を辿った第7章がとくに興味深かった。ついで、まえがきと第1章も著者の哲学的立場を理解するにはよく読むべきだろう。些事ではあるが、著者は本書の中では一貫して独訳のキルケゴール全集を引用しており、原語=デンマーク語の全集ではない。まえがきにはヨアキム・ガルフによる優れたキルケゴール伝について触れられているが、これも2004年に独訳、翌年に英訳が出ているのでいずれかで読んだと思われる。2018/08/20
左手爆弾
4
キルケゴールの「実存」を発展的に読んだり、実存の語を大きくとらえすぎないなど、従来のキルケゴール研究とは異なる視座を提供する。入門書的な雰囲気のようでいて、元々は博士論文で提示した問題を引き継いでいるため、必ずしもわかりやすくはない。個人的にはイロニーやフモール、さらにはアドルノにも引き継がれる否定弁証法など、キルケゴールの人間的魅力云々よりも理論的道具立てに興味を持った。だが、同時にキルケゴールが何故現代では以前ほど読まれなくなったのかもなんとなくわかった気がする。2015/06/14
Ex libris 毒餃子
4
キルケゴールの従来のイメージを覆す一冊。ガルフの伝記の影響が大きいか。憂愁と積極性が反復している性格なのか。彼の著作を読んでから本書を読むとイメージが変わり再読したくなる。2015/04/30
illsign
3
キルケゴールの教科書的な説明に全く納得していなかった身としては、我が意得たりの気持ちだった。個人的には大満足です。2017/06/07