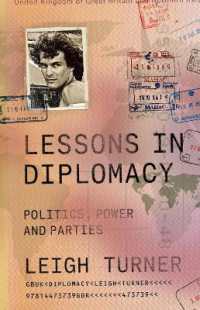内容説明
本巻の特徴は、安全保障をめぐる憲法的・法的世界の発掘と可視化にある。世間一般に抱かれている憲法(学)に対するイメージとは異なり、あえてより「現実」を踏まえた議論に軸足を移すことで見えてくる論点の提示に重点を絞って、安全保障問題への立憲主義的思考の浸透とそこでの問題発掘に主眼を置いた。
目次
安全保障の立憲的ダイナミズム
1 日本の安全保障と憲法(九条の政府解釈のゆくえ;主権・自衛権・安全保障―「危機」の概念としての憲法制定権力;九条論を開く―“平和主義と立憲主義の交錯”をめぐる一考察)
2 軍の持続的な統制は可能か(軍隊と憲法;文民統制論のアクチュアリティ;裁判所と九条;インテリジェンスと監視)
3 立憲主義は新しい安全保障論にどう対応するか(立憲・平和主義の構想;リスクの憲法論―自由に対峙する環境と災害;安全保障の市民的視点―ミリタリー、市民、日本国憲法)
著者等紹介
水島朝穂[ミズシマアサホ]
1953年生。早稲田大学法学学術院教授。憲法学、法政策論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
10
日本政府は憲法9条2項が禁止する戦力を「自衛の為の必要最小限度の実力を超えるもの」としてきた。つまり「必要最小限度の実力の行使」に当たるかどうかが本来の憲法上の関心事な筈だ。ところがAという行為は集団的自衛権に当てはまらないから合憲で、Bは当てはまるから違憲という「量的概念」で議論されている。集団的自衛権は「質的概念」だ。「必要最小限度」の集団的自衛権はあり得ない。なぜこんな事になるのか。それは「必要最小限度の中に集団的自衛権も含まれる」と、あたかも個別的自衛権の範囲内にある様に論理をすり替えられたからだ2015/07/04
Kazuo
5
岩波書店「シリーズ日本の安全保障」第3巻。「本巻の特徴は安全保障をめぐる憲法的・法的世界の発掘と可視化にある。より『現実』を踏まえた議論に軸足を移すことで見えてくる論点の提示に重点をしぼった」。第4章執筆は石川健治氏、この人は本を書かないが、その論文は、ほとんどの場合、抜群に深く鋭い。「目的が手段を正当化するわけではなく、目的が正当でも過剰な手段を用いれば違憲・違法の評価をすべきだ、というのが、立憲主義・法治主義の要諦である」。われわれ日本人が、誇りを持って自由に生きるための必要最低限の要件である。2016/02/13
かじやん0514
3
いまの憲法学界の九条を中心とする、平和主義をめぐる議論を網羅できる。よく言われるような厳密な絶対平和主義を、護憲論が唱えたことはないことは共通認識になった方がいいと思う。2014/12/20
かじやん0514
1
再読。憲法学界の行方が非常に心配になってしまった。2015/04/01
check mate
1
主要論文は通読。蟻川論文が白眉。2015/02/19
-
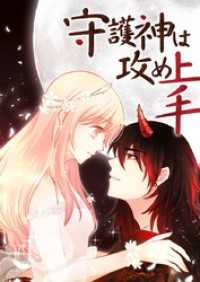
- 電子書籍
- 守護神は攻め上手【タテヨミ】第92話 …