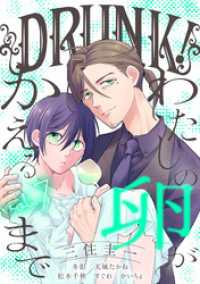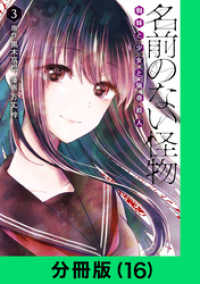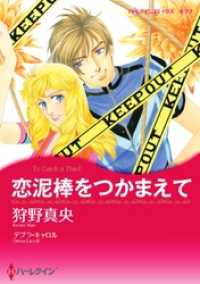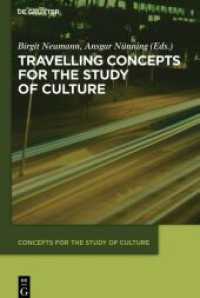内容説明
お互いを支え合い助け合うのが人の常ですが、生きるうえでは、さまざまな揉めごと、争いごとを避けて通ることはできません。負けるが勝ちを実践した藤原道長、殿上人のいじめに立ち向かう平忠盛、継母からの辱めに耐える小林一茶…。対決と熱狂、心中の葛藤、戦いの悲しみなど、古典のなかに描かれた「たたかう」人びとの姿を探ります。
目次
1 闘志を燃やす
2 闘いの知恵
3 対決と熱狂
4 戦いの悲しみ
5 男女のいさかい
6 心中の葛藤
著者等紹介
久保田淳[クボタジュン]
1933年生。東京大学名誉教授。日本中世文学・和歌文学専攻
佐伯真一[サエキシンイチ]
1953年生。青山学院大学教授。日本中世文学・軍記物語専攻
鈴木健一[スズキケンイチ]
1960年生。学習院大学教授。日本近世文学専攻
高田祐彦[タカダヒロヒコ]
1959年生。青山学院大学教授。平安時代文学専攻
鉄野昌弘[テツノマサヒロ]
1959年生。東京大学教授。日本古代文学専攻
山中玲子[ヤマナカレイコ]
1957年生。法政大学教授・法政大学能楽研究所所長。日本中世文学・能楽専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
新地学@児童書病発動中
96
「たたかう」という切り口で日本の古典の精髄を味わう書。非常に面白くて、夢中になって読んだ。戦だけではなく、男女のいさかいや心中の葛藤など「たたかう」ことを多面的に捉えている。これまで全く馴染みのない歴史的な事実を知って、驚くこともあった。例えば武士同士の戦を喜んで見物した人々がいたそうだ。浅ましいが、私達の心の中にはそんな嗜好が潜んでいるのかもしれない。編者はそれを鋭く指摘している。「戦いの悲しみ」の章が一番印象に残る。「汝を殺したりとても、我が子生き帰りて来まじ」(『古今著聞集』より)(続きます)2017/10/23
山がち
2
シリーズの他の巻に負けず劣らず信じられないほど面白い話をたくさん引っ張っている。元寇でよく言われるような日本は一騎打ちという文化であるというのをあっさりと否定し、だまし討ちや集団戦法を使っていたというようなことが書かれていたり、「大江山」の歌は小式部内侍が強く切り返したのではなく、むしろ「助けを求めたけどまだなんです」と相手に乗っかる形で冗談を言っていると解釈をしたり(それも、景樹の説に拠っている)讃岐典侍日記で、内侍は他の人の言うことをまるで無視して、自分の世界に没入してお参りにいくなどが特に印象的だ。2013/11/28
ケンチャン
1
シリーズ第四弾。この時代にもだまし討ちが普通に行われていたという内容は驚き。一対一の正々堂々とした戦いは、演劇の世界ならではのものだった。巴に関する話が連続で掲載されていて、充実していた。色々な内容が盛り込まれていて、興味深かった。2014/10/14