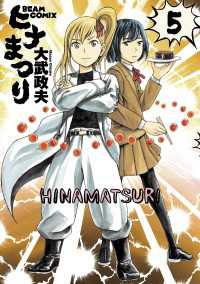出版社内容情報
歴史学から災害史・環境史を問う試みが意欲的に行われる今、古代史研究から現代に向けて言えることは何か。考古学および古気候学・地質学など自然科学諸分野の成果を参照しつつ、火山噴火・地震・津波等の自然災害、また飢饉・疫病等が社会にもたらした被害の実態を復元し、災害に向き合った人々の姿や復興の様子に迫る。
内容説明
歴史学から災害史・環境史を問う試みが意欲的に行われる今、古代史研究から現代に向けて言えることは何か。考古学および古気候学・地質学など自然科学諸分野の成果を参照しつつ、火山噴火・地震・津波等の自然災害、また飢饉・疫病等が社会にもたらした被害の実態を復元し、災害に向き合った人々の姿や復興の様子に迫る。
目次
“災いと病”を考える
古代の災害と社会
貞観地震・津波による陸奥国の被害と復興
古墳時代の榛名山噴火
飢饉と疫病
律令制の成立と解体の背景としての気候変動
“個別テーマをひらく”十和田の火山泥流
“個別テーマをひらく”開聞岳の火山灰
座談会 新しい“災害史・環境史研究”へ―古代からの展望
著者等紹介
吉村武彦[ヨシムラタケヒコ]
1945年生。明治大学名誉教授。日本古代史
吉川真司[ヨシカワシンジ]
1960年生。京都大学教授。日本古代史
川尻秋生[カワジリアキオ]
1961年生。早稲田大学教授。日本古代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
2
貞観津波、十和田の平安噴火2024/09/14
イツシノコヲリ
1
古代の災害史に関する論考が並びます。なんといっても古気候の中塚氏の論考の目新しさが印象に残る。中部日本におけるセルロースの酸素同位体比の分析は見事なものだと思うが、数十年単位の不作の発生が数年・数百年の不作よりも人間活動において大きな影響を与えることを簡単な数理モデルで明らかにしていることも興味深い。座談会でも環境決定論の話がメインです。他にも火山噴出物や津波堆積物といった考古学の論考もあり、勉強になりました。2024/04/04