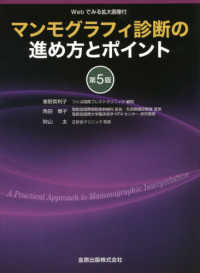出版社内容情報
「これながいきの薬ある。のむよろしい。」――この台詞を見ただけで中国人が思い浮かぶ人は多いだろう。だが現実の中国人は今こんな話し方をしない。フィクションの中で中国人を表象するこうした言葉遣いは、実在した話し方が元になっているのか。また歴史的にどのようにして中国人と結びつけられるようになったのだろうか。
内容説明
「これながいきの薬ある。のむよろしい。」この台詞から中国人を思い浮かべる人は多いだろう。だが現実の中国人は今、こんな話し方をしない。近代の日中関係のなかでピジンとして生まれたことばは創作作品のなかで役割語としての発達を遂げそれがまとう中国人イメージを変容させつつ生き延びてきた。前著『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』から十一年を経て“アルヨことば”をめぐる歴史の旅があらたに始まる。
目次
序章 “アルヨことば”にまつわる疑問
第1章 宮沢賢治は「支那人」を見たか
第2章 横浜ことばとその時代
第3章 “アルヨことば”の完成
第4章 満洲ピジンをめぐって
第5章 戦後の“アルヨことば”
終章 「鬼子」たちのことば
著者等紹介
金水敏[キンスイサトシ]
大阪大学大学院文学研究科教授。1956年4月大阪生まれ。1982年東京大学大学院人文科学研究科博士課程退学。大阪女子大学助教授、神戸大学助教授を経て、2001年より現職。日本語文法の歴史的変化と役割語(言語のステレオタイプ)を研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
absinthe
鉄之助
1.3manen
はる
-
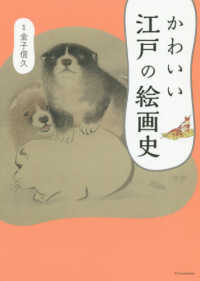
- 和書
- かわいい江戸の絵画史