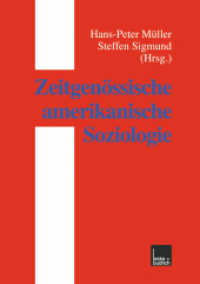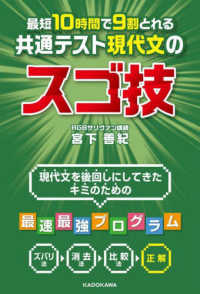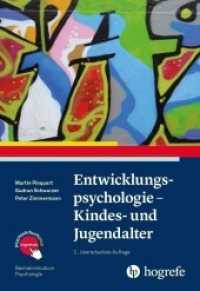出版社内容情報
フィールドワークをふまえて民族誌を著わそうとする人類学者たちにとって,「書く」行為とは何か.彼らは世界各地の民族・文化とどうかかわり,それをどのように記述してきたか.「劇場国家」論などで知られる著者が,レヴィ=ストロース,マリノフスキー,ルース・ベネディ
内容説明
『ヌガラ』や『ローカル・ノレッジ』で知られる文化人類学者クリフォード・ギアーツが一九八八年に出版した本書で向けられる主たる関心は、「人類学者はどのように書くか」という問題である。そこで主要な人類学者たち、レヴィ=ストロースやエヴァンズ=プリチャード、マリノフスキー、ルース・ベネディクトらの民族誌のテキストを読み解き、観察する側と観察される側の関係性の中で露わになる独善性や作為性をえぐりだしながら、いま人類学者が民族誌を書くことの意義を根本的に問い直してゆく。
目次
第1章 あちら側にいるということ―人類学と執筆の場面
第2章 テクストに内在する世界―『悲しき熱帯』の読み方
第3章 スライド写真技法―エヴァンス=プリッチャードによるアフリカ文化の透かし絵
第4章 目撃者としてのわたし―マリノフスキーの子どもたち
第5章 われわれ対われわれでない人びと―ベネディクトの旅
第6章 こちら側にいるということ―ともあれそれは誰の生活か
著者等紹介
ギアーツ,クリフォード[ギアーツ,クリフォード][Geertz,Clifford]
1926年、サンフランシスコ生まれ、2006年逝去。文化人類学者。マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア大学などを経て、元プリンストン高等科学研究所教授
森泉弘次[モリイズミコウジ]
1934年、東京生まれ。早稲田大学大学院(ロシア文学)、北海道大学大学院(英米文学)に学び、現在、青山学院女子短期大学名誉教授、日本翻訳家協会事務局長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。