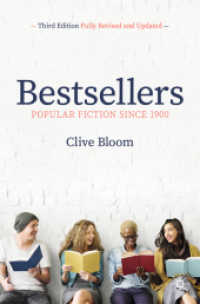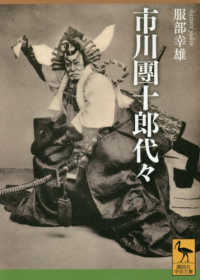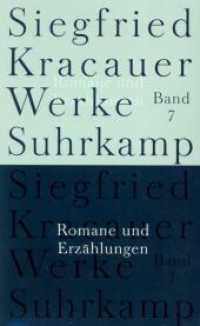出版社内容情報
戦後日本社会とは何だったのか――社会の枠組みを根底で規定した高度経済成長を世界史的同時性の中に位置づけるとともに,政治的・経済的支配システム,人口動態,地域開発,企業社会,競争と貧困などのさまざまな切り口を通して,戦後日本社会の構造的特質とそこに生きた人びとの姿を描き出す.
内容説明
戦後日本社会とは何だったのか―社会の枠組みを根底で規定した高度経済成長を世界史的同時性のなかに位置づけるとともに、政治的・経済的支配システム、人口動態、地域開発、企業社会、競争と貧困などのさまざまな切り口を通して、戦後日本社会の構造的特質とそこに生きた人びとの姿を描き出す。
目次
1 戦後日本社会の枠組み(二〇世紀のなかの日本―「高度成長」の歴史像;人口の動きと社会構想)
2 政治的・経済的支配の構造(戦後エリートの肖像―政界、官界、財界の高度成長;自民党政治の変容―無党派層と一九七〇年代半ばの転換;企業社会―「豊かさ」を支える装置;「開発」のなかの地域社会)
3 社会変容のなかの「競争」と「貧困」(「貧しさ」のかたち;新自由主義下の社会―同意調達の諸相)
著者等紹介
安田常雄[ヤスダツネオ]
1946年生。神奈川大学特任教授。近現代日本思想史
大串潤児[オオグシジュンジ]
1969年生。信州大学准教授。近現代日本史
高岡裕之[タカオカヒロユキ]
1962年生。関西学院大学教授。近現代日本史
西野肇[ニシノハジメ]
1969年生。静岡大学准教授。近現代日本経済史・経営史
原山浩介[ハラヤマコウスケ]
1972年生。国立歴史民俗博物館准教授。近現代日本史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
お抹茶