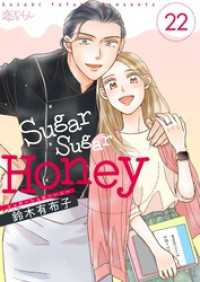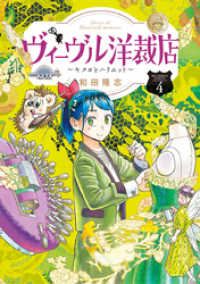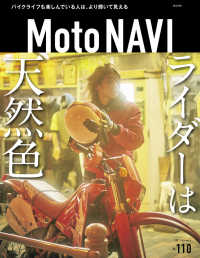出版社内容情報
言文一致体の担い手という役割から、当初はじき出されていた女性たちは、書くことによって、いかにして公共空間における主体としての自己を獲得していったのか。明治初期の新聞や雑誌に表出された膨大な言説の分析を通して、表現の場における「近代」の本質をジェンダーの観点から鋭く抉り出した好著。
内容説明
言文一致体の担い手という役割から、当初はじき出されていた女性たちは、書くことによって、いかにして公共空間における主体としての自己を獲得していったのか。明治初期の新聞や雑誌に表出された膨大な言説の分析を通して、表現の場における「近代」の本質をジェンダーの観点から鋭く抉り出した好著。
目次
第1章 女の声を拾う(「婦女童蒙」と新聞;女が書く投書―一八七〇年代後半;声の圧殺―一八八〇年代初頭;制度の包囲;書くことをめぐる闘い)
第2章 女の読み書きを追う(「開化の時代」の「女権」と「女徳」;「メディアの時代」の女の読み物;「小説の時代」の女の読み物;女が書く小説)
第3章 女の小説を読む(“和装”と“洋装”―『薮の鴬』;「女徳」の動揺―「許嫁の縁」;“女の運命”の凝視―「こわれ指環」;挫折する共同性―「萩桔梗」;“新しい男性”の創造―「苦患の鎖」;氷の海の下で)
第4章 女の文体を計る(書簡文的規範と逸脱する本文;『いらつめ』あるいは流行雑誌;一人称というモード;女のスタイルブック)
著者等紹介
平田由美[ヒラタユミ]
1956年生まれ。大阪外国語大学外国語学研究科修士課程日本語学専攻修了。京都大学人文科学研究所助手、大阪外国語大学助教授、同教授を経て、大阪大学大学院文学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。