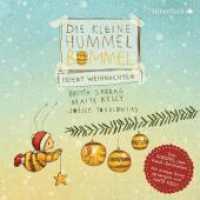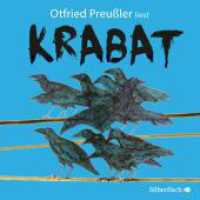出版社内容情報
近代になって誕生した探偵小説というジャンルは,〈都市〉の成立とも密接な関係を持っている.近代とは何か,都市における欲望のありようとは何か,探偵小説は多くの示唆を与えてくれる.19世紀から今日までの探偵小説を通じて,探偵小説を消費する精神の土壌を分析し,その言語の有する問題性にまで迫る.
内容説明
近代になって誕生した探偵小説というジャンルは、“都市”の成立とも密接な関係を持っている。近代とは何か、都市における欲望のありようとは何か、探偵小説は多くの示唆を与えてくれる。一九世紀から今日までの探偵小説を通じて、探偵小説を消費する精神の土壌を分析し、その言語の有する問題性にまで迫る。
目次
第1章 猫と探偵と二十世紀(起源と模倣;猫と探偵;探偵とは誰か;ある興味;ディスクールの不安)
第2章 緋色の研究(ザディグの方法;デュパン、あるいは深さのゲーム;緋色の研究;最後の挨拶)
第3章 探偵小説の屈折と戦争(ABC;義眼のなかの動機;童謡殺人;都市の名づけえぬ顔;狂気の通路)
第4章 探偵のディスクール(想起と眠り;遊歩、蒐集、そして探偵;解釈の詐術)
著者等紹介
内田隆三[ウチダリュウゾウ]
1949年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。専攻は社会理論・現代社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ecriture
6
探偵小説という形式を分析し、さらにはその形式をとらせた社会の分析を同時に行う。探偵小説はある種の不安や社会変革を消費し、中流階級の平穏へと回帰するタイプの「心地よい眠り(夢)」追求・及び悪魔祓いの側面がある一方で、社会に潜む隠れた事実を暴露し、その相対化・空洞化の指摘となる側面も併せ持っている。世界大戦をはさんで「狂気の裏に隠れた正気(という狂気)」型の作品が増えたとする整理は笠井などでもお馴染みだが、ハードボイルド作品の「人間的深みでない都市そのもの」の分析は参考になった。2012/01/14
あんすこむたん
1
探偵小説から様々な理論を導いている書。第3章は特にいい。2017/09/19
テトラポッド
0
お勉強兼趣味。む、難しかった…。2023/04/09