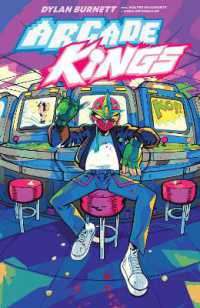出版社内容情報
遠く離れた戦争は、「銃後」の社会や人々の暮らしをどのように変えたのか。戦争の本質に「銃後」から迫る。
内容説明
かつてない規模で軍人・軍属が戦場へ動員されたアジア太平洋戦争。しかし、多くの民衆の日常は「銃後」の社会のなかで営まれていた。遠く離れたアジアや太平洋の戦争は、農村や都市の姿を、そしてそこで生きる人々の社会関係を、どのように変えたのか。「銃後」の成立から崩壊までをたどりながら、戦争の本質に迫る。
目次
プロローグ
第1章 「非常時小康」
第2章 村と戦争―「忍従」の村
第3章 パリのような街で
第4章 建設の戦争
第5章 地方翼賛文化運動―戦下の民衆論
第6章 銃後崩壊
エピローグ―「銃後史」のゆくえ
著者等紹介
大串潤児[オオグシジュンジ]
1969年、東京生まれ。東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。現在、信州大学人文学部准教授。日本現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バルジ
2
空襲や疎開といった大東亜戦争末期の「銃後」ではなく、日中戦争から連続する日常の中でのよ「銃後」社会を複層的に記述しており面白い。本書の問題提起は広がりを持つが、個人的には戦争に動員される社会と人々の中でも、決して一枚岩かつ権力の都合の良いようには動かなかった点を強調したい。本書は様々な史料から社会状況を概観するが、当時散々唱えられた「個人主義廃絶」のように個人の決定権を制限しようとするも、賃金の高い職場への移動、職場内での不満は抑えようが無い。戦争は日常を消していくが銃後社会では人々の感情までは奪えない。2022/12/18
ぞだぐぁ
0
戦前の日本が驚く程現在と重なって見えることに驚いた。農業が食えなくてどんどん町に出て行ってしまうとか、商業より工業の方が稼げるとか。あと、兵役と少子化と理由は違っても労働人口が減った社会状況とか。2017/03/21
-
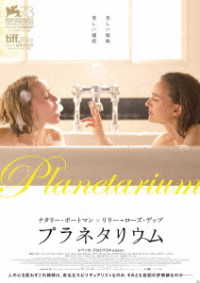
- DVD
- プラネタリウム DVD